
|
|
|
2002/12/19
「タイムスリップ」
--ジョーン・フォアマン女史が集めた「タイムスリップ」例には、謎を解くもう一つの鍵が認められる。サレー州ウィズレー・クム・ピアフォードのタレル・クラークという女性が、夕べの祈りへ行くために、現代の道路を自転車でサイクリングしていた。突然、その道路が野原の小道になり、彼女はそこをとぼとぼ歩いているらしい。尼僧の服装になっている。十三世紀の農夫の服装の男が見える。彼はたたずんで彼女に道を譲る。それから一ヶ月後、村の教会のなかに坐っていて、彼女は教会が昔の状態に戻るのを見る。床は土のまま、祭壇は石造り、尖塔窓。現代の教会では聖歌隊しか歌わない単旋律聖歌を、茶色の僧服の僧侶たちが朗々と合唱する。この瞬間、タレル・クラーク夫人は、自分が教会の後ろのほうにいて、行事の進行を眺めているような気持ちになる。彼女に起きたことは、視点の移動ということらしい。彼女は、だれか別の人間の目で事物を眺めている。野原の小道をとぼとぼ歩く婦人の目だ。教会の後ろのほうに立って眺めている女の人の目だ。--
(コリン・ウィルソン「世界不思議百科」関口篤訳、青土社より)
*タイムスリップにはいろいろ事例があり、有名なものでは博物学者イワン・T・サンダーソン夫妻がハイチで見た「五百年昔のパリ」の風景がある。だが二入に同行したフレッドという男はまったくそのようなものを見なかった。
--やがて体が前後に揺れるような感じになってきた。少し眩暈もする。フレッドの名前を呼んだ。すると彼の白いシャツがたちまち遠ざかって消えた。
その時なにが起きたのかよく覚えていない。私たちは彼を追いかけようとした。しかし、目がくらんだ。粗い大きい縁石と思ったものに腰をおろした。フレッドは、どうしたのかと言いながら走って戻ってきた。しかし、最初はなにを言ったらいいのか分からない。彼が煙草を保管している。まだ数本残っているはずだ。彼はそこに坐って私たちに一本づつ渡した。彼のライターの火が私の目の前で消える。それと同時に十五世紀のパリも、ふっとかき消えた。私の目の前には元の限りなく続く薮の茂みとサボテンとむき出しの土しかなかった。妻もライターの焔を見た瞬間に「帰還」した。フレッドは何も見ていない。私たちの話に彼はキツネにつままれたような顔をした。しかし、疑う様子はない。三人でそこに坐ってトラックを待っていただけだと言った・・・。
--後に村の若者一人がサンダーソンに次のように言った。「旦那、あれ見た。ちがう?旦那、それ変だと思ってる。だけど、見たいと思ったら、いつでもそれ見ることできるよ」。--
この有名な話しとともに、ヴェルサイユ宮殿で1789年のヴェルサイユに迷い込んでしまった二人の英国婦人の話しも採録されている。これも有名な話しだ。タイムスリップについては夜話で私の体験談も載せている。未来の自分に心だけタイムスリップしたというものなのだが、この本で指摘される「昔の時代の、他人の目で見る」という共通点について、ちょっと感覚が似ているなと思った(私の場合は「未来の時間の、自分の目で見る」だったのだが)。本文引用の例はいわゆる「幻覚」のたぐいのようにも思えるが、そこに一種超能力のようなものの存在を感じさせる。霊媒というものと紙一重のところにいるように思う。一方サンダーソン博士の体験は幻覚ではすまされないものがある。夫人も一緒に見ていること、現地人は「知っていた」こと。煙草の火で消えたこと(煙草に火をつけたとたん我に返るというのは、怪奇談でしばしば聞かれる結末だ)。-それにしても「体ごと」タイムスリップすることは無いようだ。サンダースン博士の場合もフレッドという男に言わせれば、「その最中」ただ並んで坐っていただけだというのだから。
2002/12/18
「テレビにうつるもの」
--所用のため、友人のAさんと長野市内で会った。Aさんは、「ちょっとの間待ってね、すぐ終わる用があるから」といって私を巫女さんのところへ連れていった。この巫女さんは、死者の霊を招いてくれたり、悩み事や病気を治してくれる方なのだそうで、Aさんは私を待合室において奥へ入ってしまった。大分待ったけれどなかなか出てこないので、奥へ覗きに行ったところ中から声がかかった。
「そこにいる人、中へお入りなさい」
中へ入ると坐れという。坐ると、
「あなたの背に死者がのっている。その人は男の人で六十二歳位の人、頭は白髪まじりで角刈りにしている。脳の病いで死んだ人だ。非常に業の深い人だから、あなたはその霊が救われて、離れるまで供養しなければならない。そうでないと、あなたが不幸になる」
そういって、ろうそくと線香を包んでくれ、
「しっかりするんだよ」
と肩をたたいた。帰りに角刈りの人、角刈りの人と考えながら帰ったけれど思い当たらない。それで、このことは忘れることにした。
その夜中、なかなか眠れないので天井を見ていると、テレビの方がチラチラ明るい。起き直って見ると画面いっぱいに男の人が映っている。驚いたことに角刈りであった。間もなく消えたけれど身震いがしてついに眠れなかった。
それから一ヶ月ばかりたって久し振りに亡夫の実家へいった。この家のしきたりで訪れる人はまず仏壇に挨拶するのが例であったので私も拝礼し、ふと頭を上げて見ると、写真が目についた。それが角刈りのおじさんだった。そして先夜のテレビの人そっくりであった。私はこの家の当主である亡夫の甥を呼んで聞いてみた。
「この人は誰?」
「おやじだいね」
「お父さんはいくつで亡くなった?」
「六十二でいったわね、脳出血でね」
ここまで聞いて私はえたいの知れない身震いで、しばらくは立ちつくした。
(長野県・多田ちとせ/文)--
(松谷みよ子「現代民話考[第二期]Ⅲラジオ・テレビ局の笑いと怪談」より)
*話しの流れからすると、テレビの影は単に「暗示」にかかった結果なのかもしれない。角刈りの人角刈りの人と考えながら帰っているくらいだから、夜、入眠時にありがちな幻覚として、昼間に刷り込まれた「角刈りの人」がブラウン管の中に顕れたように感じたのかもしれない。ただ、最後の事実との一致は偶然と片づけるには少し不気味すぎる感がある。テレビの中にえたいのしれないものが顕れるという例は、結構多いようで、例えば「心霊写真」「心霊ビデオ」のひとつの典型として、「電源の入ってないブラウン管に不気味な顔が・・・」というのがある。また、これは5、6年前のことだったと思うが、終わったテレビのサンドストームの中に、「死後の世界の映像」が映りこむという「現象」が、テレビ番組で特集されたことがある。いささか胡散臭い話であるが、さしずめ映画「ポルターガイスト」の中の、「サンドストームに引きずり込まれる少女」のようなイメージだ。この映画でもサンドストームは死者の世界ということになっている。電気と水は死者を呼び易いというが、常時電気の通じているテレビというものは、死者の世界との接点に近い場所なのかもしれない。
2002/12/16
「金しばり」
--これは金しばりにあった人の話です。ある女の人が夜、寝ていると、ベッドの回りを誰かが歩く気配がしました。ふと目を覚ますと足元に、白い服を着た小さな女の子が立っていました。体は動きません。そこでその女の人は以前、金しばりにあった時は自分の信じる宗教のお題目やお経を唱えればいいと聞いていたので、一生懸命目を閉じて心の中でお経を唱えていました。するとさっきまでベッドの回りを歩いていた気配がなくなったので、安心して目を開けると、目の前にさっきの女の子の顔があり、「何、拝んでんの」と言われたそうです。
[出所]話者は、大阪の女子短期大学生。一九八八年六月に三原が聞く。--
(三原幸久ほか編著「魔女の伝言板」白水社より)
*「金しばり」は手ごろな怪談話としてしばしば登場するシチュエーションだ。私自身もそうだが、だいたい30代までには体験しなくなるたぐいのもので、若年期特有の感覚なのだろう。この話は「おさまった」と思った直後、絶望的な結末をむかえるという、怪談としてはいささかできすぎな感もしなくはないが、面白い噂話として採録した。金縛り最中に何か得体の知れない(人間のような)ものに出くわすというのはこの種の話では定番の筋書きだが、体がまったく動かない絶望的状況において何らかの異質な気配を感じるというのは非常に恐怖をかきたてられるものである。私自身、大阪の某ホテルで就寝中、開かない窓が突然開いて、黒ずくめの男が入ってきて、ベッドのまわりをぐるぐる回られるという経験をしたことがあるが、直後より朝まで一睡もできないほど、恐怖をかきたてられた。別項でも書いたが、白いドレスの女があらわれて、「俺じゃなくてあいつのところに行けよ」というようなことを心の中で呼びかけたら、ほんとうに友人の部屋に行って「悪さ」をしたというようなこともあった。学生時代はそれこそ毎晩のようにいれかわりたちかわり妙なものが顕れたが、別項に書いた、坊主の集団に取り囲まれたり、外から入ってきた大男に首をしめられたというようなことが特に怖かった経験として記憶に残っている。
2002/12/15
「ろくろ首二話」
--若狭国の百々茂右衛門という侍が、夜更けに士町の水谷作之丞という人の高塀の外を通ると、塀の上に女の首があってそれがあちこち移動している。茂右衛門は不審に思って月影に透かして見ると、それは作之丞の侍女で、その首は茂右衛門を見覚えているのでこちらを見てにっこり笑う。茂右衛門は無礼な奴と思ったので持っていた杖で首の頭をそっと突くと、首は邸内に落ちた気配がした。
丁度その頃作之丞の侍女は熟睡していたが、急に叫んで目をさましたので、傍に寝ていた下女が「どうなさいました」と聞いた。すると侍女は「今恐ろしい夢を見た。旦那様と話をしていると門前を通られた百々茂右衛門殿が、わたしを見てお持ちになっている杖でいきなり頭を叩かれた。あまりの痛さに逃げ出したところで目がさめた」という。翌日侍女は作之丞にこの話をしたが、「たあいのない夢だから気にするな」といわれた。その後茂右衛門も塀の上で見た侍女の首の話をした。作之丞は暫く考えていたが、これは侍女が轆轤首に違いないと知り、侍女を密かに呼んでその事をいうと、侍女は恥じて直ちに暇をとって寺に入り、一生を尼として過ごしたという。(原著:藤沢衛彦「妖怪画談全集」日本編上)
*この「首」は「魂」に近いものなのだろう。首がじっさいに抜けたところは描かれていないからだ。これを不可解な不思議話として置いておくと、次の話はある程度医学的に説明できそうな話である。
--俳諧師の遊蕩一音という男が新吉原で美貌の遊女と馴染んだが、仲間があの女は轆轤首だというので、居続けをして様子を窺うと、夜中にその遊女の首が枕から三十センチも伸びた。一音が驚いて大声を出したので不寝番の妓夫太郎や棲主たちが飛んできて一音をなだめて酒肴でもてなし、これが評判になると店に痕が付くからどうか内緒にしてくれと平身低頭した。考えるに飛頭蛮のように首が数メートルも伸びたり飛んだりするのは嘘であるが、異質のものは気がゆるむと首の皮が伸びてこうしたこともあるものである。(原著:伴某「閑田耕筆」巻之二)
(以上、笹間良彦「図説日本未確認生物事典」柏美術出版より)
2002/12/14
「餓鬼」
--伊勢から伊賀へ抜ける街道で、私の後から一人の男が急いできて、
「私は大阪の者ですが、今ここへ来る道筋で餓鬼に取り憑かれ、飢餓感でこれ以上一歩も進めず難渋しています。御無心ながら、何か食べ物を頂戴できないでしょうか」
と言った。
なんと不思議なことを言う人だと思いながら、
「旅行中で食べ物の蓄えはありませんが、切り昆布なら少し持っています」
と答えると、
「それで結構です」
と言うので、与えると直ちに食べてしまった。
私は、
「餓鬼が取り憑くというのは、どういうことなのですか」
と問うと、男は、
「目には見えませんが、街道筋のところどころで、餓死した人の霊や怨念が現れます。その怨念が餓鬼となって、道行く人に取り憑くのです。餓鬼に取り憑かれますと、突然飢えがきて、体力がなくなり、歩くこともできなくなります。私は、過去に何度もそのような経験をしたことがあります」
と答えた。この男は、薬種商人で、常に諸国を旅行して歩いている人だった。
その後、播州国分のある寺院の僧に、そのことを尋ねると、
「私も、若い頃、伊予で餓鬼に取り憑かれたことがあります。それ以来、諸国行脚の旅をするときは、食事の際に出た飯の一部を取りおいて、それを紙に包んで懐に入れ、餓鬼に憑かれたときのために貯えておきます」
と答えた。
なんとも不思議な話だ。--
(花房孝典編著「大江戸奇怪草子」三五館より)
--俗に言う「ひだる神」のことである。別項でも書いたように思うが、私も中学のころ、登山中にこれに近い状態に陥ったことがある。歩いていて、突如ふらっとし、体中の力が抜け、動けなくなった。崩れ落ちるようにしゃがみこんでしまう。・・・これは「ひだる神」か?それなら、と震える手で荷物からビスケットを取り出した。それをたった一欠け口に含んだとたん、急に体に力が戻り、けろっと元どおりになった。爽やかな晴天の下、尾根筋を縦走中のことで、特段きつい日ではなく、脱水症状とも違うようで、なんとも不可思議だったことを覚えている。--
2002/12/12
「水蜘蛛の怪」
--我が家に按摩療治に来る七都という座頭から療治を受けながら直接聞いた話である。
七都は上総の国夷隅郡大野村の出身で、村には幅十間ほどの川が流れているそうだ。
七都は二四歳のときに失明して座頭になったが、彼がまだ二二、三歳のころ、ある日その川に魚釣りに出かけた。
その川には「樅の井戸」と呼ばれる大変深い淵があり、対岸は薮に覆われ、昼なお暗く寂しいところだが、そこはまた魚影の濃い特別の場所だったので、七都はいつも樅の井戸に釣り糸を垂れていた。
その日は、なかなか釣れず眠くなってうつらうつらしていると、水の中から蜘蛛が出てきて、七都の足の指へ糸をかけ、また水の中へ潜り、再び出てきてまた同じように指に糸をかけた。七都は夢かと思いながら、ふと足元を見ると、なんと足首のほぼ半分に糸がかけられていたので、驚いてはずし、糸を水際に立つ杭に巻き付けておき、何事が起こるのかと、息を凝らして見ていると、ややあって、何者かが水中から、
「いいか、いいか」
と声をかけた。するとその声に呼応するように藪の内から、
「いいぞ」
という声が聞こえた。
その瞬間、糸の巻かれた杭はポキリと折れて水中に引き込まれてしまった。
その後は、あとをも見ず、慌てて家まで逃げ帰ったということだ。
(根岸鎮衛「耳袋」より)
2002/12/11
「・・・」
--神奈川県三崎町油壷にある旅館の離れに、アベックの幽霊が出て、別れ話をする。「アンタ、自分の主張というものがないの!?」
と女性の幽霊が言うと、男のほうはただただ黙り込む。--
(原著:松永克広「妖魔がさ迷う怨霊列島」グリーンアロー出版社、広坂朋信「東京怪談ディテクション」希林館より)
2002/12/7
「雪の午後 帰ってきた男」
--彼女は、Rという、東京にある商事会社の開発事業部の新入社員である。
今年初めて東京に雪が降った日のこと、海外出張に出ていたN氏という35歳の男性社員が社に戻ってきた。
「ただいま帰りました」
「あれ?早かったのね」
「ええ」
N氏は、予定ではこの日の夜8時くらいに社に戻るはずであったが、今はまだ昼休みである。
出張の疲れのせいか、N氏の顔はどこか蒼ざめていて精気がなかった。
「ご苦労だったな。荷物を整理したら今日はもう帰っていいぞ。今夜は積もりそうだ」
課長が窓の外を眺めながら言った。
「むこうも積もっていたかね」
「真っ白でした。雪はいいですよね。なにもかも、きれいに埋めてしまう・・・」
「どうした、詩人みたいなこと言って」
課長がN氏のほうを振り返る。
「いや、なんていうか、雪の中で死ぬっていうのは、きれいでいいなあって・・・。ほら、昔あったじゃないですか。やくざが、雪の中で刺されて、真っ赤な血しぶきを上げて死んでゆく映画が・・・。かっこよかったよなあ。真っ白な地に真っ赤な血・・・」
N氏はスーツケースの中の荷物を整理しながらつぶやいた。
「昔はやったもんな、仁侠映画」
N氏と課長は大の映画好きだった。
「はい、お茶」
女性社員が茶碗を出す。
「ありがとう」とN氏。
「ああ、うまい。やっぱり普段何気なく飲んでて気づかないけれど、外国から帰ってきたあとの一杯は心にしみるな。生き返るよ、ほんと」
しばらくすると、窓の外の雪がだいぶ激しく降りだしてきた。
「テレビつけてみろ、天気予報やってんじゃないか」
課長の言葉で、テレビの近くにいた社員がスイッチをつけた。
お昼のニュースである。
「ただいま入ったニュースですが・・・」
深刻そうなニュースキャスターの顔。画面右下の”飛行機墜落”の文字。
「・・・ボーイング××機が、アンデス山脈北東部に墜落したもようです」
「あっ、これNさんが乗るはずだった飛行機でしょ」
女性社員が身を乗り出した。
「よかったなあ、おい、早く帰ってきて正解だったよ。あれに乗ってたら、今頃おまえはオダブツだ」
課長がN氏の肩を叩いて笑った。
「・・・乗客の中には日本人もいたもようです・・・大使館の確認によりますと、乗っていた日本人は・・・」
ニュースキャスターが墜落機の日本人乗客の名前を読み上げる。すると、お決まりのカタカナ表示で死亡者の名がテロップされる。
「・・・さん、・・・さん、・・・さん、・・・」
「あっ!」社員一同ほとんど同時に叫んだ。
「Nさん」
一斉に社員はN氏のほうを向いた。
N氏は顔を上げた。
その顔はまるで万年雪のように蒼白だった。
一瞬の沈黙。しんしんしんしん・・・雪の音。
「そうなんだ・・・俺、死んじゃったんだよな・・・」
N氏はポツリとつぶやくと、静かにみんなの顔を見渡して、寂しげに笑った。そしてドアを開けると廊下へ出ていった。
「Nさん!」何人かがあとを追う。
しかし、すでにN氏の姿は廊下にはなかった。
同僚がN氏の席を見ると、彼が持っていたスーツケースや荷物はなかったが、机の上に出張先でまとめた書類と、取り引き成立の証明書が乗せてあった。
しばらくの間、みんなその場で凍りついたかのように動くことができなかった。やがて、課長がわれに返ったようにつぶやいた。
「責任感のある奴だったからな」
課長の言葉に、数人の女子社員のすすり泣きがかぶさった。
この日、夜になっても雪はやまず、東京は久しぶりにかなりの量の積雪を記録したという。
(会社の怪談調査委員会「カイシャの怪談」ワニブックスより)
2002/12/4
「たたり神」
--私は先日、某地域の社寺取材に行ってきたのだ。そこから帰ってきた数日後、知人から「取材はどうでした?」と電話を貰った。
私と同じく神仏好きな人だったので、色々盛り上がってると、彼は突然「その近辺にある××神社に行きました?」と声を落として聞いてきたのだ。
「ああ、あのわけのわからない渡来神を祀った神社ねぇ」
変わった名称の神社だったので、私はちゃんとチェックしていた。今現在、祭神はオーソドックスなものになってるが、本来は海の向こうから来た神を祀った場所である。
その渡来神の素性は不明。好奇心をくすぐられる場所だ。
「行こうと思ってたんだけど、時間がなくなっちゃって。次回ということにしたんです」
言うと、彼氏、しばし黙ったのちに、こんな話をし始めたのだ。
「僕の親戚が以前、夕暮れにそこの神社に行ったら、杖をついた身の丈三十センチほどの白髪の老人に会ったんですよ」
「へ?」
それこそ、神サマか。
杖をついた小さな老人って、北海道にいるというコロボックルって感じじゃない?妙にラッキーなイメージだ。
「それは、いいものを見ましたねぇ」
ちっ。無理してでも行ってみればよかったな、と、思いながら答えた途端、
「はぁ。いえいえ。その親戚、老人を見た一週間後に亡くなってしまって」
彼は低い声で返した。
「亡くなったって・・・」
「気になったので調べてみたら、神社に小さな老人が出るっていう話は、その近辺では、よく知られたことだったんですよ。そうして見た人はみんな、そのあとですぐ死んでいるっていうんです。昔からある話らしくて・・・。だから土地の人は絶対に、夕暮れ以降はそこの神社に行くなって、子供に教えているそうで」
「・・・」
「危険なので、今は神社に門をつけて閂をかけてあるんです。でもね、時々、誰が開けたわけでもないのに、閂が外れているんだそうです。そうすると、事情を知らない誰かが入ってしまったりして」
やややや、やめてくれえぇぇっ!---
(加門七海「うわさの神仏」集英社より)
2002/12/3
「東尋坊の怨霊」
--真夜中、こんな所に来るのは、自殺者か、よほど神経の図太い人間だ。墓場の肝試しの百倍以上も怖い。
林の中ほどにさしかかったとき、何故か懐中電灯の球が切れてしまった。ここに来る途中、コンビニで買った七八〇円の安物だ。私は、ちきしょう、と呟きながら懐中電灯を捨てた。
しばらくは動かずに目をならしたが、まったく明かりのない深い森の中では、一メートル先も見えなかった。
足を踏み外したら最後、自分が霊安室に横たわる羽目になる。
手探りで観光客用の公園がある方角へ向かった。そこにはわずかだが街灯があったはず。
ゴツン。何かが頭に当たった。恐る恐る手で触れる。靴・・・?足だ!!
振り払おうとした手が空を切った。消えた!?
木にぶつかりながら、無我夢中で逃げる。この東尋坊は、飛び降り自殺の次に首吊り自殺が多い。怖いと思う気持ちが、木の枝を足と錯覚させたのか。いや、たしかにバスケットシューズの感触だった。しかも、木の枝なら消えるはずがない。
やっとのことで林を抜け、公園の中の街灯の下に出た。ハアハアと息をきらしながらベンチに座ると、オレンジ色の淡い光があたりを照らしていた。目の前には岸壁が迫っている。
と、突然、人の気配を感じてギョッとした。隣のベンチに誰かが座っている!!たしか、自分が座るまえは誰もいなかったはずだ。
私はゆっくりその方向に顔を向けた・・・。
いる!母親らしき人影と小学三年生くらいの男の子が、前を見つめたまま寂しそうにたたずんでいる。
思わず手を合わせお経を唱えた。すると親子は立ち上がり、岸壁のほうに歩き出した。
そして母親は子どもを抱え上げると、真っ暗な海をめがけてパッと飛び降りた!
私はアッと声を出す以外、なすすべがなかった。恐ろしさのあまり、心臓が喉から飛び出しそうだ。あれは幽霊だ。直感でわかる。私はふたたび、一人で来たことを後悔した。
ベンチ横の、自殺防止用の公衆電話(命の電話)にはいり、宿泊している旅館に電話をかける。二人が帰っていたら呼び出そうと思ったのだ。しかし、いくら十円玉を入れても落ちてしまう。壊れているのか?
プルーッ、プルーッ、どこかにつながった。でも、なぜつながるのか?
私はダイヤルしていない!
「・・・シク・・・シク・・・シク・・・」
受話器の向こうから、女のすすり泣きが聞こえてきた。霊界とつながったのか・・・。私の体は、氷の柱のように動けなくなった。
追い打ちをかけるように、誰かの手が右足をつかんだ。見ると、電話ボックスの下から青白い女の手が・・・。ボックスの外には誰もいない。あるのは手だけ。しかもそれは、半透明に透けている!
立て続けの怪事に、すっかり頭の中がパニックになってしまった私は、電話を切り、十円玉を入れ、また切っていた。何度もその行為を繰り返すうち、やっと我に帰った。
電話ボックスをはい出て、防風林を迂回し、車を止めてある舗装道路まで走る。車に乗り込むと、けっしてルームミラーを見ないようにし、全速力で旅館に戻った。
落ち着きを取り戻したのは、旅館の駐車場に着いたときだった。取り乱していては、部下にしめしがつかないと思い、深呼吸をして玄関にはいる。
部屋に戻る途中、エレベーターでいっしょになった仲居さんが、私を見るなり怪訝そうな顔をしてこう言った。
「あ、お兄さん、誰かつれてきたね。私の体の半分(手で体を縦に切るしぐさをして)が、ジーンと痛くなってきたよ」
「本当に?」蚊の鳴くような声で応えるのが精一杯だ。
「家まで、ずっとついて来られたら、いったいどうすればいいのだ?」
部屋に戻ると、真っ青な顔をした二人が私の帰りを待っていた。口々に今夜体験したことを報告しあうと、大の大人でもトイレに行けないほどの恐怖が襲ってきた。
結局、私たちは、外が明るくなっても寝つけなかった。---(ガルエージェンシー代表渡邊文男「怨霊調査報告書」ごま書房より)
*この本は非常に興味深い。「日本で一番有名な探偵」(しかも霊感がある)がその培ってきた調査能力を駆使して日本中の”問題物件”を実地調査のうえ、報告書の形で提示している。面白い。ちなみに東尋坊は昔東尋坊という坊主が悪行のすえ追いつめられて飛び降り死んだためその名がついたという岸壁で、自殺の名所である。飛び降り自殺となると海に叩き付けられて死ぬように思うが、ここは水が浅くて岩が透けて見えるようなところで、寧ろ岩に叩き付けられぐちゃぐちゃになって死ぬらしい。崖自体はそれほど高いわけではなく、海まで降りて遊覧船に乗ることができる。
2002/12/2
「帰ってくる死体」
男の人が二人、友達同士で雪山にのぼったんですよ。ところが吹雪にあって、遭難しちゃって、なんとか山小屋にたどりついたんですけど、一人の方が死んじゃったんですね。それでやっぱ、一緒っていうのはなんじゃないですか。だから小屋の外に雪掘ってうめたんですよ。それで一晩ねて、朝、気がついたら隣りにそのうめてきたのがねてるんですね。ぎょっとしちゃって、生き返ったのかと思ったけどやっぱり死んでるし、でもその日も吹雪がやまなくて、また山小屋に泊まったんだけど、その死んだ友達を、しょうがないし、もっと遠くへうめてきたんですよ。で、朝目がさめると、また隣にねてるんですよ。で、まだ吹雪はやまなくて、もうどうしようもなくて、そうだ、それでビデオもってたんです。それで、じゃどういうことになってるか、夜ビデオ、セットしとこう、ということでセットしといたんですね。で、朝、また隣にいるから、ビデオみたら、最初は自分が一人でねているのがうつっている。そのうち、むくっと自分がおき上がって外へ出ていったんですって。で、しばらくしたら自分が戻ってきたんですけど、それが死んでる友達をかついでたんですって。それで自分の隣にこうやってねかせて、無意識にさみしくて掘り出してきてたっていう。
[出所]一九八五年に当時二十代前半の女性から渡辺が聞く。
(渡辺節子ら編著「魔女の伝言板」白水社より)
*この話しはさまざまなバリエーションをもって広まったウワサ話である。その影響範囲は日本にとどまらないようだ。映画「ブレアウィッチ2」のオチなど、このネタに通低するものがある。
2002/12/1
「隣室の客人」
--ところで、いまは「天城」の話である。
ある日のこと、男の客がふたり連れで隣室に入ってきた。
といっても、そのことに気づいたのは深夜になってからである。おたがい異なった地方で頑張っていた友人同士が、この宿で落ち合って旧交を温めている、そんな感じのおだやかな話し声がずっと聞こえてきた。声の質から考えて、教員とか地方の公務員とか、そういう職業の人間だと判断した。
わたしも夜型の人間ではあるし、夜中に仕事をするので、たいして気にならないものの、時計が三時、四時をさすころにはうとうとしはじめる。
さてこちらも就寝しようとしたが、隣室の声がうるさくて眠れないのである。いったん気になりだすと話し声が耳について、ますます眠りから遠ざかってしまう。
いったいこんな夜更けまで、何について話しているのだろう。よく通る声のわりには言葉の意味はもうひとつ判然としない。はて、日本人なのだろうかなどと考えていると、ひとりの男が相手の非をなじりだし、なじられた男はくどくどと弁解しているようすだ。
結局、こっちはその話し声に邪魔されて、安眠できないまま朝を迎えたが、頭重で気分の悪いことおびただしい。気がつくと、男たちの声も聞こえなくなっていた。
ともあれ、隣室の迷惑も考えぬ客というのは不愉快な存在であるから、あくびを噛み殺しながら階段を降りると、帳場へ怒鳴りこんだのである。
「ホント、ひでえ迷惑なんだってば。昨夕、隣りの部屋に泊まってたの、どこの、なんていう奴?」
「あら、隣りの部屋って?」
ちょうど五十歳前後の帳場のおばさんは、首を傾げた。
「だから、隣りの、菊の間-」
彼女はわたしの顔をまじまじと見ると、ほんとうに嬉しそうにニターッとほほ笑んでいった。
「昨夕、お二階には、山田先生、あなたしか泊まっていませんよ」
「そんなばかな・・・現に、昨夕・・・ぼくは」
「宿帖、見ますか、ホラ」
「・・・」
(山田正弘「怪談 幻妙な話」二見書房より)
2002/11/30
「動く棺桶」
1812年8月9日、カリブ海に浮かぶバルバドス島で、トマス・チェイス卿の棺桶を石の階段の下の同家の地下納骨所におろすことになった。重い石蓋を横に動かしてランプの光で中を照らした。様子が少しおかしい。すでにそこに入っている三つの棺桶のうちの一つは側面が下になっている。赤ん坊の死骸が入っている棺桶は隅で頭の部分を下にして突っ立っている。明らかにだれかが、この墓地の神聖を汚した。しかし、不思議なことに、むりやりに押し入った形跡はどこにもない。棺桶を元の場所に並べ直して納骨所を封印した。土地の白人たちはニグロの労務者の仕業に違いないと噂した。トマス・チェイスは奴隷所有者で、残酷かつ無慈悲な男だった。チェイスよりほんの一ヶ月前に死亡して最後に地下納骨所に入った棺桶は、彼の娘のドーカス・チェイスだが、彼女は奴隷に対する父親の野蛮な仕打ちに抗議して絶食し、それで死んだとの噂だった。
それから四年が過ぎた。1816年9月25日、小さな棺桶をその地下納骨所にまた入れることになった。死骸は生まれてまだ十一ヶ月のサミュエル・ブルースター・エイムズ。今回も納骨所はひどく乱れていた。四つの棺桶すべてが、床にひっくりかえっている。トマス・チェイスの棺桶は重い鉛の内張りで、持ち上げるだけで八人の男手を必要とするものだ。これもひっくりかえっている。今度も棺桶を元の場所にきれいに並べ直して、納骨所を封印した。
次に納骨所を開いたのはその七週間後だった。今度はサミュエル・ブルースターの死骸を収容するためである。この男は同年の四月の奴隷の反乱騒ぎで殺され、ほかの場所に仮埋葬されていた。今度も地下納骨所は、むちゃくちゃな荒廃ぶりだった。棺桶が混乱状態でひっくりかえっている。ニグロの奴隷たちの仕業であることを疑わないものはなかった。彼等が仕返しでやったに違いない。しかし、どんな方法でやったか、これが謎だった。大きな大理石の蓋は、そのたびにセメントで封印している。その封印が破られた形跡も封印をし直した形跡もない。
この納骨所に最初に入ったのはトマシーナ・ゴダード夫人の棺桶だが、これは手荒く扱われたのが原因と考えられるが、板が壊れてがたがたになっている。これは、応急処置で針金で縛って壁にたてかけた。この納骨所は三・七メートルと二メートルの縦横しかない。少し混んできた。子供の小さい棺桶を成人の棺桶の上に置いた。それから再び納骨所を封印した。
バルバドス島はこの奇怪な噂でもちきりになった。嬉しくない好奇心の対象になったのはキリスト教会とそこのトマス・オーダーソン牧師である。噂をふりまく雀たちに対しては、彼はじっと我慢するしかなかった。しかし、社会的地位が高く丁寧な応対が必要な人士には次のように説明した。自分と治安判事は最後の事件以来、同地下納骨所の調査を継続している。問題はどんな方法でそこに侵入したかだ。秘密の扉はあり得ない。床も壁面も湾曲した天井も完全に堅固で、割れ目も裂け目もない。洪水も出水も原因でないことを牧師は確認した。納骨所は地表から約60センチ下だが、固い石灰岩をくりぬいた造りだ。出水があればそのマークが残るはずだ。それに、重い鉛の内張りの棺桶が水に浮くことなどおよそ考えられない。土地の黒人たちは次のように噂した。あの墓地には、なにか呪いがかかっている。超自然の力が棺桶を動かした。言うまでもないがオーダーソン牧師はこの考えを退けた。
次の埋葬はいつ行なわれるか。全バルバドスが関心を持ち興奮した。それは1819年7月7日だった(十七日とする説もある)。トマシーナ・クラーク夫人の死骸が、杉材造りの棺桶に収容されて納骨所に入ることになった。前回の封印でセメントをふんだんに使ったので、これを除くのにかなりの時間を必要とした。セメントをやっと除去した。次はドアだが、これが頑として開かない。さんざん苦労したあげく、トマス・チェイスの大きな鉛張りの棺桶が元の位置から約二メートル弱も移動して、ドアをふさいでいることが分かった。針金で巻いたゴダード夫人の棺桶を除いては、ほかの棺桶もいずれも乱れている。これで出水が原因でないことが、確実に証明された。木の板が動かない出水で、鉛張りの棺桶が動くことは絶対にあり得ない。
バルバドス総督のカンバーミア卿がまっさきに納骨所へ入った。彼は徹底的な調査を指示した。しかし、結果は前にオーダーソン牧師が言ったことと同じだった。悪漢がいたとしても、この地下納骨所にこじ入る方法はいっさいあり得ない。秘密の引窓もない。水の侵入口もない。納骨所の再封印に先立って、カンバーミアは床に砂をまくよう命じた。侵入した人間の足跡が残るはずだ。彼はさらに自分の個人用封印も使用した。こうすれば、開いて封印し直しても必ず痕跡が残る。
八ヶ月後の1820年4月18日、カンバーミア卿の総督官邸でパーティが催された。話題は例によってあの地下納骨所のことになった。ここで総督は提案した。前回の対策処置に効果があったかどうか、全員で行ってみよう。行ったのは総督と牧師と二人の石工を含む九人だった。セメントと封印には異常がない。まずこれを確認した。次に石工がドアを開いた。ふたたびそこは混乱状態だった。子供の棺桶は、下の主室に通ずる石段の上に移動している。トマス・チェイスの重い棺桶は、天地がさかさまだ。異状がないのは、針金で巻いたゴダード夫人の棺桶だけだった。床にまいた砂には、なんのマークもない。今度も石工がハンマーで壁を叩いて調べた。秘密の入口の類はやはりない。分かったのは、この謎が解けないということだけだった。カンバーミア卿は棺桶を別の場所に埋葬し直すよう命令した。その後、この地下納骨所は空っぽになる。--(「世界不思議百科」コリン・ウィルソン、青土社より)
2002/11/28
「電話ボックス」
新宿から甲州街道を西へ車でひたすら走ると、深夜なら一時間半もあれば高尾駅にたどりつく。駅前の交差点を右折して高尾街道に入り、最初に現れる交差点を左折してまっすぐ進むと、都営八王子霊園が左手にある。
--霊園の入口近くに行ってみると、ぽつんと寂しく電話ボックスが設置されている。それにまつわるこんな話もある。
ある夜中に、電話ボックスの近くを車で通りかかったF氏(三五歳)は、ヘッドライトの光の中に突然小さな女の子の姿が浮かび上がるのを見た。急ブレーキをかけて止まり、外に出ると、五、六歳の女の子が道路にしゃがみこんで白墨で路面に絵を書いている。
こんな夜中にひとりでどうしたと声をかけると、お母さんを待っているといって、幼女は電話ボックスを指さした。なるほど女の人が電話している。
それにしても夜中である。外に子供を放置しているのはよくない。しかも危うく事故になりかけた。F氏は幼女の手を引いて、電話ボックスまで連れていった。ドアをノックして「この子のお母さんですか?」と声をかけると、うしろから「はい」という声がした。ふりむくと背の高い女がいて、F氏を見下ろしていた。彼はその女の手を引いていたのである。(同朋舎「ワールド・ミステリー・ツアー13④東京篇」6.現代の都市伝説を追う(小池壮彦)より)
2002/11/22
「天井下がり」
--イラストレーターのKさんが、十数年前、大学時代に住んでいた都内のアパートで体験した話である。
真夜中、Kさんが寝ていると何かがバサッと顔にかかった。
寝ぼけてそれを何度か手で払っていたが、ハッとその奇妙なものの存在に気づいて目が覚めた。そして、あらためて顔にバサリとかかるそれを、両手でつかんでみた。
「えっ?髪の毛?」
不思議に思ってそれをつかんだままグイッと手元に引っ張ってみる。
するとそれは、天井のあたりに根を生やしているかのような手応えで返ってきた。
「これは一体何だ!」
びっくりして飛び起きて、部屋の電気をつけてみた。
髪の毛だった。
天井から、だらーりと長い長い真っ黒の髪の毛が出て、その先端がKさんのベッドのあたりまで垂れ下がっている。
しかも、もっと怪異なことに、その髪の毛のヌシが天井からヌッと姿を現しているではないか!
それは女だった。
女の顔が、ちょうどプールの水面からぷっかりと、鼻から上だけを出したような状態をそのまま水面を天井に置き換えて、逆さにしたような状態・・・、そして、その女の長い髪の毛がすらすらと垂れ下がっているのである。
一見色白の美人、その目はまばたきもせず、じっと正面を見つめている。
従って、下から見上げているKさんと目が合うようなことはなかったが、Kさん自身が目の前の光景をにわかに信じることが出来ず、ただ、その不思議なものを観察していたという。ずっとその間、その天井から出ているその怪異なものは微動だにせず、そこにあった。
「夢だ。これは夢にちがいない。そうでなければおかしい」
Kさんは自分でそう言い聞かせ、一端表に出て頭を冷やし、気を静めてまた部屋に戻った。
やっぱりそれがある!
その時はじめて恐怖感が全身を襲った。そのまま部屋へ入ることが出来ず、友人宅に泊めてもらったのである。
翌朝、アパートに帰ってみると、もうその怪しいものの姿は消えていた。
ただ、納得しないKさんは、天井裏に入り込んで調べてみたが怪しいものは何もなく、また、それっきり怪しいことも起こることはなかったという。--
(中山市朗「妖怪現わる」遊タイム出版より)
2002/11/19
「自由ヶ丘の女」
--こんな町だから出たのも若い女性である。男子大学生二人組がドライブの帰りに自由ヶ丘駅前の電話ボックスで髪の長い女が座り込んでいるのを見かけた。声を掛けると終電を逃して困っているという。家は鎌倉だというので送っていくことにした。鎌倉で彼女を降ろして、もと来た道を戻り、また自由ヶ丘駅前を通りがかったところ、先程の電話ボックスの前に、身なりも背格好もそっくりの女が、やはり同じ姿で座り込んでいた。--(「東京怪談ディテクション」広坂朋信、希林館より)
2002/11/10
「穴」
--ある夜、用務員のおじさんが学校をまわっていると、家庭科教室でミシンの音がする。おじさんが鍵をあけて中に入ってみると女の子がミシンを踏んでいる。何をしているのかとたずねると、宿題がどうしてもできないのでやっていると答える。不思議に思い、どこから入ったかというと、あそこからと指さす。みると、小さな穴があいていた。東北・北海道の集いで参加者の女性から聞いた話。宮城県・松谷みよ子/文--
(「現代民話考[第二期]Ⅱ学校」松谷みよ子、立風書房より)
--この話しで思い出すのは、「夜話」で書いた江戸時代の話。とある宿で、今日は外に出るなと言われた人が、外へ出たいとうろうろしていた。それが部屋から姿を消す。ただ表に通じる小さな穴の周りにおびただしい血痕がべたりとついている。外へ出たいという気持ちが魔物に魅入られて、穴から外へ引きずり出されたのだろうと。。。
2002/11/3
「南島のカッパ」
--沖縄県島尻郡久米島。私の父は十三年前六十七歳で死亡しましたが、父の健在中で、私が五、六歳のころのことです。そのころ私たちは久米島の仲泊に住んでいました。梅雨のころのある日のことです。私は兄と二人で部屋の中でニックルー(レスリングのような遊技)をしていましたが、疲れたので雨戸を五寸ほど明けて外を眺めていました。突然、背丈二尺五寸くらいの、幾分青味がかった小人のようなものが現われて、庭に置いてあった二個のファンドガーミ(水がめ)の前をゆっくりと歩いて行きました。今まで見たこともない奇妙な生き物ですので、私はびっくりして、何だろうかとじっと見ていたら、その小人のようなものが、まるで立って歩いている大きな蛙のような恰好をして、よちよちと、いうような感じで歩いて行きました。私たちはその横姿を見たわけです。別に私はその小人のようなものに対していたずらをしたわけでもありませんが、二、三日経ってから、私と私の兄が同時にヤーツー(やいとのこと)をされたような刺激を受けました。私はヘソに、兄はチンチンの先にやいとをされたようになり、それが水ぶくれしたので、父に「お前たちは、その変な者にいたずらをしただろう」と叱かられたのを覚えています。
(註/この談話で注目すべき点は、その怪物は「ブナガヤ」かなとも思われるが、色が青味がかっていたという点である。日本本土のカッパは青いが、沖縄のキジムナーは赤いというのが定説であるから、この証言は異例に属している。)話者・長田朝久。出典・山城善光著「ブナガヤ・実在証言集」(球陽堂書房)。
(「現代民話考1河童・天狗・神かくし」松谷みよ子、立風書房より)
2002/11/1
「くすぐるルサールカ」
トローイツァの日以後にやむにやまれぬ用で森へ行くときは、この草(ヨモギ)を携えて行かなければならない。ルサールカが必ず駆け寄ってきて、こう尋ねる。「手になにをもっているの?ポルィニ(ヨモギ)、それともペトルーシカ(セリ科の植物)?」「ポルィニ」と答えると、ルサールカは、「棚の下へ(ポトィン)隠れろ!」と大声で叫んで、さっと走りすぎる。このときすばやくルサールカの目をめがけてヨモギを投げつけねばならない。もし「ペトルーシカ」と答えたら、ルサールカは、「オー、わたしのかわいい人!」といって、その人が口から泡を吹いて倒れ、息絶えるまでくすぐり続けるんだ。(「ロシアの妖怪たち」斎藤君子、大修館書店より)
2002/10/25
「キキーモラ」
--家の中に出没する妖怪には女の妖怪もいる。紡ぎ女キキーモラ(シシーモラ、ドモジーリハ、オギボシナともいう)である。キキーモラという名称はキキーとモラのふたつの構成要素から成り立っていて、前半のキキーは鳥、とくに雄鳥の鳴き声を表わし、後半のモラは古代スラヴの神話に登場する死神の名である。このふたつが結合してできたキキーモラとは、雄鳥のように泣いて人の死を悼む死神である。彼女は背中の曲がったおばあさんで、ぼろをまとい、いつも髪を振り乱しているという。身体があまりに小さいので、風に吹き飛ばされることを恐れて外には出ないのだという人もいる。人に姿を見せることはまれで、足を踏み鳴らしたり食器を割ったりして、物音だけで自分の存在を知らせ、住人を脅して家から追い出す。ヴャトカ県サラープリスク郡でこんなことがあった。
新築の家にキキーモラが現れた。姿は見えないのに、人のうめき声がするんだ。テーブルにつくやいなや、「テーブルを離れろ!」という。いうことを聞かないと、暖炉の上から毛皮のコートを投げつけたり、ポラーチ(ペチカの上から対面の壁にかけて板を張った寝床)の上から枕を投げたりして家の人たちを追い出してしまう。
ところが、人間を追い出したキキーモラが今度は逆に人間に追い出された。
ある家で毎晩キキーモラが床を歩きまわり、ドンドンと大きな足音を立てた。それだけでは足りず、皿をガチャガチャいわせ、壷を割るようになった。そんなわけで住人が家を捨てたために、この家は空き家になった。そこへ熊使いが熊を連れてやってきて、この空き家に住みついた。ところがキキーモラは相手が熊とは知らず、熊にかかっていってもみくちゃにされ、ウンウンうめいてこの家から逃げ出した。それでこの家の持ち主一家が戻ってきた。それから一か月経ったころ、この家の近くにひとりの女がやってきて、子どもたちに、「猫はもういなくなったかい?」と聞いた。「猫は元気だよ。仔猫を生んだよ」と子どもたちが答えた。するとキキーモラはくるりと向きを変え、「もうだめだ!あの猫一匹でも獰猛だったのに、仔猫どもまでいっしょじゃあ、近づくこともできやしない」といって、引き返していった。
キキーモラは自殺者を埋葬した場所や、かつて道路だった場所など、不浄な場所に建てられた家に棲みつくともいう。彼女が姿を現わすのはその家に災いが起きる前触れとされ、恐れられてきた。ドモヴォイもキキーモラも家に棲みついている妖怪であるが、前者は祖先の霊と結びついていて、家の守り神的性格を持っているのに対し、後者は死神に近い存在である。--(斎藤君子「ロシアの妖怪たち」大修館書店刊より)
「かくれ岩」
かつて、青梅に実在した白い色をした奇岩である。街道沿いにあるため、その岩の前を人がよく通る。遠くから見ると、その通る人の姿が、岩にとけ込んでしまったように見えるのだ。まるで、姿が消えたように見えるため、「かくれ岩」という名前がついた。特に服が消えたように見え、顔と手足のみが歩いていくようにも見えたという。何やらユーモラスで楽しげな妖怪岩である。--(山口敏太郎「江戸武蔵野妖怪図鑑」けやき出版刊より)
「白い鳩(タウベ)」
マグデブルクの法学専攻の学生数人が19世紀の末、冗談気分で女占い師のところに行ったんだ。ひとりに女はこう予言した。「白い鳩(タウベ)がおまえを殺すだろう」警告されたやつはケタケタと笑った。「どうして白い鳩がおれを殺せるってんだい?」そいつは予言をすぐに忘れた。何十年かして、そのあいだに彼は名望ある弁護士になっていたんだが、盲腸を切ってもらわなくてはならなくなった。そこで何人もの教授が勤めている名高い病院へ行った。手術室で、白い手術着をつけた外科医が彼に挨拶した。「よろしく、教授のタウベです」こうして予言は実現した。外科医の手にかかって死んだというわけだ。--この話は女性採録者の父親が、1989年2月にゲッティンゲンを訪れた際に語った。彼は説明にこう付け加えた。「当時外科医は手術室では白い上着を着ていた。いまでは緑のを着ているが」この患者は彼の父親の友人だったという。彼をはじめ、いっしょに女占い師を訪ねた人びとは、遺された夫人のために遺産の整理を手伝ったとき、はじめて予言のことを思い出した。(ロルフ・ヴィルヘルム・ブレードニヒ編「悪魔のほくろ」池田香代子、真田健司訳、白水社刊より)
「炙り子」
鹿児島市下福本の清泉寺跡には建長二年銘の毘沙門天の立像摩崖仏がある。その右には高さ二メートルほどの阿弥陀摩崖坐像もある。その奥には中世の五輪塔や層塔のくずれたのがある。現在養魚池のある谷はアブリコの谷といわれ、そこにも摩崖仏がある。「アブリコが出るからゆくものでない」といわれた恐ろしい、音のしない、不気味なところである。アブリコとは焼いた子という意味で、以前火葬場があったらしく、恐らく古い風葬地であったと思われる。--
「狐火二態」
--神奈川県津久井町三井の高城賢治さんがその実見者ですが、現われた場所は津久井湖に臨む薬師様の山腹でした。
「峰の薬師様の山には、昔から横引きという道があってね。今ではその道の下に立派な県道ができましたが、昔は細い横引き道が、二つの村をつなぐ主要道路だったんです。狐火はその道へよく出たんですね。私が見たのは十六歳のときだから、昭和二年の七月十三日か十四日でした。日まで憶えているのは、お盆の花を買うので、中野町まで行ったからですね。その日は自転車で出掛けて、その帰り道でしたが、そのとき日暮れ間近で、雨も少し降ってきました。坂道を下りながら、ふと薬師様の下の横引き道を見ると、変な明りが一つ点いて、それが見る間に二つ三つと、次第に数が増えてゆくので、”あっ!狐火だ!”と、思ったね。自転車を止めてしばらく様子を見ていると、点々と点いた火がどんどん横に広がって、しまいには何十という火が一線に並んだわけですね。ところがね。それが一度にパッ!と消えてしまうんですよ。するとまた元のように点いて、そんなことを何度も繰り返しましたが、実に不思議に思ったですね」
--高遠町芝平地区の鈴木捨男さんの実に珍しい話がこれです。
「その奇妙な火を見たのは、今から三十五年位前ですから、昭和二十六年頃のことです。自分の家の前には田圃があって、その先は傾斜した土手になっているんですが、その田圃の畦道に狐火が出たんですね。その畦道と自分が立って見ていた所との間は、たった四十メートル位しかないんですよ。
それは火の玉のようではなく、赤い火炎がいくつもボーボーと燃えながら、次から次へと、左から右へ進んで行ったんですよね。それは十分間位続いたと思います。よく見ると、前へ前へと進むうち、後から順に消えてゆきましたね。季節は十一月頃でした。その頃農家の便所は大抵外にあったので、夜便所へ行こうと庭へ出たときだったですね。」(角田義治「自然の怪異
火の玉伝承の七不思議」創樹社刊より)
2002/10/24
「天女の接吻」
松平陸奥衛守忠宗の家来に番味孫右衛門という武士がいた。ある日、孫右衛門が自宅で昼寝をしていると、天女が降り来って、孫右衛門の口を強く吸った。孫右衛門は、はっと思って周りを見回したが、当然、誰もいない。「いやはや、とんだ夢を見たものだ。人に知れたらどうしよう」と深く恥じ入り、夢のことは心の奥に秘めていた。しかし、その日以来、孫右衛門が何かを言うと、口の中から得もいわれぬよい香りが漂うようになった。そのため、同僚たちが不審がり、また自身も不思議に思っていた。ある日、一人の同僚が、「さてさて貴殿は嗜み深い。いつも口中からさわやかな香りが漂ってきて、まるで匂い袋を口中に入れているようだ。いや、御奇特なこと」と言ったので、孫右衛門は、同僚に思い切って夢の話をして、それ以来、口中からよい香りが漂うようになったと打ち明けたが、その同僚もおおいに驚いたそうだ。この孫右衛門という男は、決して美男子ではなく、どこといって取り柄のない男振りなのに、どう間違って、天女は、このような男に情けをかけたのか、天女の気持ちがよくわからない。この不思議な香りは、孫右衛門が亡くなるまで消えなかったということだ。この話は、是田隠岐守の家来、佐藤助右衛門重友から聞いた話だ。(原典:大田南畝(蜀山人)「半日閑話」、花房孝典編著「大江戸奇怪草子」三五館刊より)
--天から降るモノは必ずしも良いモノとは限らない。--
「官人天より降る」
--母方の祖父が若い頃のこと。書斎に一人でいたとき、ふと外を見ると、庭の桜の枝から忽然として、衣冠の人が一人、降りてくる。よくよく見るに、盗賊には見えない。そうかといってこの辺りに公家はいないし、ましてや公家が天より降りてくる理由がない。さては心の迷いからこんなものが見えるのだろうと、眼を閉じた。しばらくして眼を開けば、まだその人がいる。また一度眼を閉じてから見ると、その人はだんだん桜の木から降りてくる。これはいけない、まだ化かされている、と、またも眼を閉じて、しばらくしてから開くと、また少しずつ近づいてくる。こんなことを三四回も繰り返しているうちに、とうとうその怪しい衣冠の人は、軒先までやってきてしまった。これは一大事と思って、眼を閉じたままで家人を呼んで「気分が悪いので布団を敷いてくれ」と言い付けて、そのまま横になって少しばかりまどろんだ。気持ちが静まってから起き上がってあたりを見回したが何事もなかった。こういう話は、曲淵甲斐守という人の身の上にも起こったという。その時は曲淵が心を静めて驚かなかったので、妖気は隣の家に移った。隣の家の主人は、すぐに狂気におちいり、腰元を切り殺してしまったと語り伝えられている。(原典:鈴木桃野「反古のうらがき」、広坂朋信「江戸怪奇異聞録」希林館刊より)
2002/10/14
「帰ってきた娘」
神田明神からお茶の水へ出る所に船宿があった。この船宿の主人夫婦に一人娘がいたが、二、三歳の頃から筆をとって書をしたためること、まるで大人のようで、両親は寵愛やむことなく、慈しんだ。両親は思うことがあって船宿をやめ、両国に引っ越したが、娘の手跡はますます上がり、近隣で評判となった。ところが文化三年(1806)に大流行した疱瘡にかかり、両親による手厚い看護の甲斐も無く、娘は六歳で身罷ってしまった。いまわの際に、母親が狂気のように泣き叫ぶのを見て、娘はか細い声で、
「ご心配には及びません。いずれ神田より来てお目にかかりますから」
と言う。母親はうつつ心に、
「その約束、必ず守るように」
と言ったが、そのときには既に娘の息は絶えていた。両親は娘を手厚く葬り、毎日嘆き悲しんでいた。
その頃、神田にその娘と同じ年頃の娘がいたが、どういうわけかしきりと、
「両国へ行きたい」
と言うので、両親が両国へ連れて行くと、船宿の主の家に入り、両親に向かって
「もう家には帰りません。こちらのお宅に置いてください」
と言うので、船宿夫婦も、娘の両親も驚き、
「これはどういう訳か」
と尋ねると、娘は傍らにあった筆をとって、見事な書をしたためた。その娘は、今まで字を書いたことなどなく、一同はその不思議さに驚いた。神田の両親は、娘を連れ帰ろうとしたが、
「私はこの家の娘です。他に帰る家はありません」
と言って承知しないため、仕方なく、神田の両親は娘を両国へ置いて帰ったという。(原典:東隋舎著「古今東西思出草子」より・「大江戸奇怪草子」花房孝典編著、三五館)
2002/10/13(11/1)
「悪魔の足跡」
冬がそれほど厳しくはないイングランドの南西部でも、1855年の冬は格別の寒さだった。2月8日の朝、デヴォンシャー州トップシャム村の小学校のアルバート・ブレイルスフォード校長は、表の玄関から外に出て晩のうちに雪が積もったことを認めた。同時に変なことに気がついた。村の道に一列に足跡がついている。いや、ひづめの跡かも知れない。最初は蹄鉄を打った普通の馬のひづめの跡と思った。しかし、よく見るとおかしい。足跡は一列だ。一つの足跡の真直ぐ前に次の足跡がある。馬なら、一本足でぴょんぴょん跳ねたことになる。二本足の未知の動物なら、綱渡りのように足跡が一列になるように注意深く歩いたことになる。さらに変なのは足跡そのものだ。長さは約10センチ、間隔はたった20センチ程度しかない。しかも、どの足跡もきわめて明瞭だ。凍った雪の上に熱い鉄で丁寧に刻印したかのようだ。村人全員がこれに気づくのにそれほど時間はかからない。彼等はがやがやとこれを南の方角に追った。ところが顔を見合わせる事態が起きた。煉瓦の壁で足跡が止まっている。そんな馬鹿な。しかし、次の発見で彼等は仰天する。足跡は壁の向こうでまた続いている。しかも壁の上の雪はきれいに積もったままだ。次に足跡は干し草の山に突き当たる。今度も同じだ。足跡はその向こうで先に続いているのに、中間の干し草の山をなにか大きい動物が乱した形跡は皆無だ。いったいどういうことだ。足跡はグースベリーの茂みの下にもついている。屋根の上にまでついている。だれかが村を訳のわからない困惑に陥れるために悪ふざけをした。そんな状況だった。しかし、この説明はまるで見当違いであることがやがて判明する。足跡はデヴォン州の田園地帯をどこまでも続いている。しかもかなり移り気のようだ。途中の小さな町や村にも立ち寄っている。リンプストン、エクスマス、タインマス、ドーリッシュなどだ。さらにはトートネスにも見られる。プリマスの港までかれこれ半分の道程だ。だれかの悪ふざけとしたら、彼は深い雪のなかを60数キロもとぼとぼ歩いたことになる。一晩でこの距離をこなすには、大急ぎだったに違いない。飛ぶが如くだ。しかし、現実には飛ぶが如くではない。あちらこちらの玄関に立ち寄っている。それから思い直してまた先へ進む。そんな具合だ。また、足跡はエクス川の河口を向こう岸に渡っているが、リンプストンとパウダーハムの間がその地点らしい。しかし、ずっと南のエクスマスにも足跡がある。そこまで戻ったのだろうか。その進路にはこれという目的はまったく認められない。場所によってひづめの跡が割れているようにも見える。いわゆる双蹄だ。当時はヴィクトリア朝のど真ん中。悪魔の存在を疑う村人などほとんどいない(悪魔のひづめは割れているという伝説がある)。男たちは銃と干し草用のフォークを手にして足跡を追った。夜が来るとドアにかんぬきを掛け、銃に玉をこめ、息をころして変事を待ちかまえた。-(「世界不思議百科」コリン・ウィルソンら著、関口篤訳、青土社)
- ふと、以下の話と関係があるのではないか、と思った。-
-熊本県阿蘇郡小国町。私が吉さんからこの話を聞いたのは吉さんが四十七、八歳になっていた昭和八、九年頃のことだ。その吉さんの若い頃の話である。木挽きの吉さんは若い頃から夫婦で山へ行って、樽丸(杉の木で樽にする木材)を取る仕事をしていた。谷川のそばの粗末な小屋で夕飯もすませ、サァ寝ようかと話しておると、どこからとなく、「ホイ、ホイ、ホイ、ホイ」と奇妙な小さいかけ声のようなものが聞こえて来る。やがて小屋の上で聞こえだし小屋がゆっさゆっさと揺れ出し、ホイ、ホイ、ホイ、ホイと妙にあとにひく声の列が、小屋の屋根の上を通っていくらしい。ヤマワロの通り道に小屋ばかけっと、小屋ばたたきつぶされるぞと山の先輩から聞いておったが、これがヤマワロちゅうもんかと急に恐ろしくなり山の神様に燈明をあげ一心にお経をあげ足音の遠くなるのを待った。夜が明けると早々に小屋をたたんで別の場所に移りましたたいと。回答者・白石忍冬花(熊本県在住)(「現代民話考1河童・天狗・神かくし」松谷みよ子・立風書房より)
2002/10/10
「神女の手紙」
早池峰から出て東北のほう宮古の海に流れ入る川を閉伊川という。その流域がすなわち下閉伊郡である。遠野の町の中で、今は池の端と呼ばれる家の先代の主人が、宮古に行った帰り道でのこと、この川の「原台の淵」というあたりを通ったところ、若い女がいて、一封の手紙を差し出した。女が言うには、遠野の町の後ろにそびえる物見山の中腹にある沼へ行って、手を叩けば宛名の人が出て来るから、渡して欲しいとのこと。この人請け負ったはいいものの、道々どうも気にかかって歩いては止まり止まっては歩きを繰り返す。そこへ一人の六部(旅僧)が通りかかり、手紙を開き読んで曰く、これを持って行くならば汝の身に大きな災いが降りかかるだろう、書き換えて進ぜようと言って、別の手紙をくれた。それを持って女に言われた沼へ行き、教わったとおり手を叩くと、はたして若い女が現われ、手紙を受け取って読むと、礼だといってきわめて小さな石臼をくれた。それに米を一粒入れて回せば下から黄金が出た。この宝物のおかげで家はやや豊かになったが、主人の妻が欲を深くして、一度にたくさんの米を掴み入れたところ、石臼はしきりに自ら回って、ついには毎朝主人がこの石臼に供えていた水がたまった小さな窪みの中に滑り落ちて、見えなくなってしまった。その水溜まりは後に小さな池になって、今も家の傍らにある。家の名を池の端と呼ぶのもそのためだという。(「遠野物語」二十七話より)
2002/10/1
羽地の山奥の村に二人のまだ若い、働き者の夫婦が暮らしていた。この夫婦は子供が欲しかったのだが、どういうわけか結婚して何年も経つというのに子宝に恵まれず、妻は毎日のようにニライの神さまに「お願いです。どうか一日でも早く、立派な赤ちゃんを授かりますように!」と祈り続けていた。
ある日、夫がいつものように村の山道を歩いていると、気のせいか遠くのほうから赤ん坊の泣き声が聞こえてくる。”こんなところに赤ん坊のいる家はないはずだが・・・”
と彼が泣き声のほうへ歩き続けると、山道を大きく外れた草陰で見たことのない、みすぼらしい身なりの若い女が赤ん坊を抱いて立ち尽くしていた。女は乳が出そうにもないほどに痩せこけ、長い髪だけが不気味に垂れ下がっている。彼女はなんとか赤ん坊をあやそうとするが、赤ん坊が腹をすかしていることは明らかだった。驚いた彼が「いったい、どうしたんだい」と声をかけると、女は涙ながらに「もうずっとなにも食べてなくて、子にやる乳さえ出ないのです。私はもうこの子を育てていくことができません。どうかこの赤ん坊をもらって、育ててやってくださいませ」と訴えた。彼は一瞬戸惑うが、赤ん坊は無邪気なかわいい顔をしており、またちょうど子供が欲しくて仕方がないときだったので、その子を譲り受けることにした。彼は喜色満面で赤ん坊を抱いて家に帰ると、妻も「まあ!きっと毎日のお祈りが神さまに通じて、赤ちゃんを私たちのもとへ届けてくれたのよ。大切に育てましょう」と躍り上がって喜んだ。
ところが、その夜、日が落ちてから妻が家のなかに明かりをともすと、夫に抱かれた赤ちゃんの姿が忽然と消えて、炎のなかに位牌が浮かび上がった。夫はさも大事そうに大きな位牌を抱いているのである。驚いた彼女が慌てて火を消すと、やはり暗闇のなかで赤ちゃんの姿が見え、泣き声も聞こえる。”なんだ気のせいだったのかしら”と彼女がもう一度、火をともすと、やはり夫の腕には位牌が抱かれている。夫もすぐ気がついて、夫婦はまた明かりを消した。それから何度やっても、赤ちゃんは明かりをともすと位牌に姿を変える。いったいどうしたことかと夫婦は恐怖に打ち震えながら眠ることもできず、真っ暗闇のなかでぐずる赤ちゃんをあやし続けた。その明け方近く、なにものかが暗闇から泣き続ける赤ん坊をじっと見据えていることに夫は気がついた。よく目を凝らすと、はっきりと二つの大きな目が赤ん坊をとらえている。それは牛のようだった。「おい。牛が家のなかにいるぞ!」と彼は叫び、その声で闇のなかから巨大な牛が角を振りかざして赤ん坊に襲いかかってきた。彼はその二本の角を両手で押さえつけながら、猛然と格闘を続けた。いつの間にか赤ちゃんは消えてしまい、気が遠くなるほどの時間が経って、夜が明けると彼が牛だと思ったものはなんと”がん”(葬式で棺桶を入れて運ぶときのための御輿)で、必死で押さえつけていたものはその二本の角棒であった。
(沖縄の伝承、「アジアお化け諸島」林巧、同文書院刊より)
2002/9/30
小学校に古いトイレがあって、一番端のを使うと、幽霊が出てくるという話がありました。ある特定の曜日の夜中の一時になると、両足のない女の人が現われて、「私の足はどこにありますか」と聞くそうです。その答えが決まっていて、「名神高速道路にあります」と答えると、今度はその女の人が「誰に聞いたのですか」と尋ねます。その質問には、必ず「カシマレイコさんに聞きました」と答えなければなりません。そう答えるとフッとその女の人は消えてしまうのだそうです。答えないとどうなるかは知りません。この話は同じ年頃の遊び友達から聞いたので、どこまで信用できるかわかりません。
[出所]話者は、大阪の女子大学生。1987年6月に三原が聞く。
カシマレイコの名を答える時に、「カは仮のカ、シは死人のシ、マは悪魔のマのカシマさんです」と答える例もある。また名前を「仮死魔霊子」と恐ろしげな当て字で書く例もある。何か交通事故に由来したハナシのようにも思える。(「魔女の伝言板」三原幸久ほか編著、白水社より)
・・・侮り難きスターリング夫人は、ポートランド・プレイスにほど近い、ハラム街のさる家にまつわる不思議な話を語っている。夫人は1934年に、その家に間借りしていた著名な冶金学者シェラード・クーパー=コウルズのもとを訪ねたそうである。学者がそこに部屋を借りたのは、こちらの方がサンベリーの自宅よりも仕事に便利だったからである。彼はこの部屋の様子を妻に見せるために、三脚を立て、カメラを置いて、居間の定時露光写真を撮った。写真を現像してみると、自分のほかには誰もいなかったはずなのに、肱掛け椅子に男が坐っているのが写っていた。何とも不思議に思ったので、ドアにしっかり鍵をかけ、フィルムを露光している間は誰も入れないようにして、さらにこの部屋の写真を撮った。すると、昔風の衣装を着た人々の写真が大きなアルバムに一冊分出来上がった。これを見せてもらったスターリング夫人は、次のようにその肖像写真を描写している。
肱掛け椅子にはピンクと白のインド更紗が張ってあった。この椅子には、ぼんやり顕現れかかった幽霊が坐っていて、その頭と口のあたりには詰綿のようなエクトプラズムが出ている。また、透明な人影をすかして、椅子の縞模様のインド更紗がはっきり見えている。しかし大多数の写真は、生きている人々の写真とまったく同じように見える---写っているのが、歴史上さまざまな時代に属する人々であることを除けば。あるものは有翼の兜をかぶり古代の鎧に身を包んだ戦士の写真であり、またあるものはウェリントン公時代のものらしい軍服を着た兵士の写真であった。可愛らしい顔をした女達の写真もあった。どの写真の人物も、はっきりしていて個性が豊かだった---それらは実体のない亡霊ではなく、生きた人間の写真のように見えた。
何かおぞましい邪悪なものを撮ったことはありますか、と夫人が訊ねると、クーパー=コウルズ氏は、時折ありましたが、そういう写真は廃棄してしまいましたと答えた。夫人はさらに、写っている人物の中で誰か身元が特定できた人はいますかと問うた。
「一人だけわかっています」と氏は答えて、私に一葉の写真を手渡した。そこに写っている老婦人は、垂れひだのある縁無し帽をかぶっていて、時代といいスタイルといい、ホイッスラーの母親の肖像画を思い出させた。「兄はこれを見ると、言いました」とクーパー=コウルズ氏は言った、「「”ばあや”の写真か、よく撮れてるなあ!」。ばあやが亡くなった時私はまだ赤ん坊だったので、顔を覚えていなかったのですが、兄はすでに物心ついていたので思い出したようです。よく似ているのにすぐ気がついて、私がどうしてその写真を手に入れたのか、訝っていました」・・・(「倫敦幽霊紳士録」J.A.ブルックス著、南條竹則・松村伸一訳、リブロポート刊より)
「数原家の倉」
幕府の御用医師で五百石を拝領する数原宗徳という人がいた。本所に居を構えていたが、屋敷内の倉に、いにしえより奇妙なものが住んでいるという言い伝えがあった。家人が倉から何か物を出したいときには、「何々の品、明日入用となります」というように前もって倉の前で言うと、翌朝、その品が倉の戸の前に出してあるということであった。約束を違えて申し入れをしないと、何やら悪いことが起こるそうだという。この屋敷はある年に大火で類焼に及んだが、その倉だけは何故か焼け残った。そのとき家来の一人が「この倉には不思議があると聞き及んでおりますがそれは平時のこと、今は非常時ですから問題はないと思います。とにかく寝る場所も無いのですから」と言って倉を開け中を片づけ、そこに寝ていると、暫くしていかにも恐ろしい形相をした坊主頭の男が現れ、「かねてからの約束を破り、許しも得ずに倉の中に立ち入り、その上無礼千万にも床を延べて寝るなどとんでもないことである。本来ならばただちに命を奪ってしまうところだが、今は非常時ゆえ、今回だけは特別に許してやる。これ以降、誰であっても、二度と倉の中に立ち入ってはならぬ」と申し渡したので、家来は慌てて逃げ出したという。以後数原家では、毎年日を決めて、倉の前で祭礼を執り行なうようになった。(「耳袋」より)
2002/9/20
怖い童謡。「さっちゃん」は実在した。全国の幸子、幸江などの「さっちゃん」と呼ばれる女の子の枕元に霊となって現れる。このとき、枕元に絵にかいたバナナを置いておくとよいが、置いてないと霊界に連れて行かれる。(「都市にはびこる奇妙な噂」桐生静+光栄カルト倶楽部編、KOEI)
2002/9/9
「泣きモノ三題」
泣く、というのは人間の初源的な感情だ・・・夢のなかで猛烈に泣いた。起きたあと、何を泣いていたのか、まったく覚えていない。でも心が軽くなったような、清々しい感じが残る。人間が人間でなくなる瞬間、即ち死を迎えるその時、どんな感情を抱くのだろう。それは人によってまちまちなんだろうけれども、ここに挙げるような感情を抱くのは嫌だと思う。死んだ後、死んだ瞬間に抱いた感情は、永遠に消えないとすれば。関東でも23区に近いエリアで、みっつの物件を挙げてみる。
ひとつ。カテドラル教会の「八兵衛の夜泣き石」・・・東京都”文京区”というだけでピンとくればかなりの歴史通。そう、江戸時代にキリシタン屋敷があったエリアで、キリシタンの拷問や処刑の行われたところだ。この奇妙な「石」・・・石仏の首を欠き、かわりに長円形の石をのせたもの・・・も、拷問に屈せず改宗を拒む八兵衛という男を生き埋めにしたとき、魂が天に昇れないように、上に乗せられたものなのだ。以来、夜になると石からすすり泣く声が聞こえ、「八兵衛苦しいか?」と石をこづくと、ごとごとと動き出すという。今は教会の中に置かれ、静かにその惨事を物語っている。
ふたつ。千葉は市川近くの国府台。江戸川をのぞむ台地、戦国時代の激戦地で敗将里見氏の城跡である里見公園にある、「夜泣き石」。もとは隣の寺域にあったものだが、現在は殲滅した里見軍の霊を鎮める「亡霊の碑」の横に移されている。北条軍に敗れ死んだ里見弘次を弔うためにやってきた娘が、余りの惨状に焼け跡の石にすがり泣き続け、遂にはそのまま死んでしまった。すると毎晩、石から悲しげな泣き声が聞こえるようになり、誰からともなく、「夜泣き石」と呼ばれるようになった。今は供養のかいがあってか泣かないというが、綺麗に整備された公園の中にあっても、この塚のあたりは気味の悪い雰囲気を感じる。
ここから程近い所にみっつ目の物件がある。古刹、弘法寺の長い石段を登っていくと、整然と並ぶ段石のなかで一つだけ、奇妙に古びて歪み湿っている石があることに気が付くだろう。江戸時代初期に有力な檀家であった鈴木氏が、徳川家康をまつる日光東照宮造営に使用する石を、船で江戸川をつたって運ぶ役目を仰せつかった。が、何故かこの市川の船着き場あたりで、船が動かなくなってしまった。鈴木氏は信仰心のあつさからこの船の石を降ろすと、弘法寺へと運び、立派な石段を造り上げてしまった。当然このことがお上の耳に入らないわけはなく、鈴木氏は責を問われ、完成した石段の中ほどで、切腹させられてしまった。以後その場所の石が無念の涙に濡れたようになっていることから、「涙石」の名がついた。これが三つ目の物件である。周りの石が皆整然と並んでいる中、ただひとつだけ、黒ずんで歪んださまは不思議に見える。ちなみにこの石を示す説明板など無いから念のため。でも60余段の立派な石段のなかで明らかに不整形な姿をしているから、すぐにわかる。泣くわけではないが涙という形で今もその感情を示しているのだ。・・・
2002/8/30
「消えるヒッチハイカー」
・・・えーと、そう、この話は僕の彼女の友達と、その親父に起こったことだ。二人は別荘から家へ帰る途中だった。田舎道を車で走っていると若い女の子がひとり、ヒッチハイクしてた。二人はその子を乗せてやったんだ。その子はうしろのシートに座った。言うには、ここから5マイルほど行ったあたりに住んでいるっていうんだ。あとは黙って窓の外を眺めてたってさ。しばらくして家が見えたんで、親父は車をそこに着けた。「着いたよ」って後ろを振り返ると、なんとその子は消えてしまっていなかったんだ!二人とも何がなんだかわかんなくなって、そこの家の人に話しをしたら、そこの家にはその子そっくりの娘がいたって言うんだ。でも、その子は数年前に行方不明になってしまってるんだ。この通りでヒッチハイクしているのを見かけた人がいたんだけど、それっきりだったってことさ。もし生きてれば、丁度その日が誕生日にあたってたってさ。(「消えるヒッチハイカー」新宿書房刊中の代表的な事例。しかし日本でも人力車の時代から似たような話しがあったらしいから、ここで採取されている1970年代の話とは別系統かもしれないし、逆に真実味を増すかもしれない。現代日本ではタクシーの幽霊話としてまことしやかに語られるものでもある。青山墓地の話は有名だ)
2002/8/22
頬撫のこと。山梨から多摩あたりに出没した妖怪で、暗い谷沿いの小路を通ると、闇の中から白い手が現れて、頬を撫でたという(「図説日本の妖怪」河出書房新社より)。小学生頃のことだったろうか。兄が夕食を終えて二階の自室に上がっていったが、程なく、どたどたと降りてきて、こう言った。「部屋の入口で、ナニモノかに頭を撫でられた」半分ひきつって半分笑っていた。気のせいと思ったのだが、この日よりしばらく妙なことが続いた。夜中に兄が目をさますと、窓から人の形をした煙のようなものが入ってきて、寝床の周りをぐるぐると周り、また窓から出ていった、とか、顔に水のようなものが垂れてきて、光にかざすと、真っ赤な血だったとか(朝起きてみるとなんともなかったのだが)、そのころ隣の私の部屋では、走る子供の影を見ていた。余りに速いし「影」だけだったので、帽子をかぶった子供ということ以上はわからなかった。原因も、また突然収束したわけも、わからなかった。
2002/8/21
異形のこと。高校の頃の話という。彼がこたつで寝ていると、
あ。
体が動かなくなった。金縛りのようだ。
目を開けた。
あ。
見ると、右手が宙に向けて伸ばされて、
その手先を「別の手」が掴んでいる。
あ。
男の腕が。すーっと中空から伸びて、つかんでいる。
手袋をはめているようでもあるが、はっきりとはわからない。
彼は、つかまれている右手を、思い切り引いてみた。
ずるっ。
何か、が引きずり出てきた。宙から、である。右手をつかむ腕の根元に、
緑色の、ごつごつとした頭の”モノ”がいた。人のかたちをしたモノが。
あ。
驚いた。驚いて、放してくれ、と思った。
放してくれ。
放せ。
誰にも言わないから。
パッ、と消えた。そのモノが何であったのか、今でも皆目見当もつかない、という。
2001/6/14
信州佐久郡北沢村名主の話し。北沢村には大明神と崇められる大きな岩があった。名主の妻は長年子供の生まれぬことを悩み、ひそかに大明神に願をかけた。37、21日のあいだ、毎夜に参詣しつづけたところ、不思議なことに懐妊したという。違いないという医師のお墨付きを得、家中で喜んでいた所、十月たっても出産に至らず、12ヶ月目にやっと出産、ところが生まれた子を見てびっくり、赤子は人にあらず、身の丈1尺5寸2分の小さな石像であった。顔は青黒く目鼻はっきりとわかり、手足腹背とも薄赤色、恐ろしい様相であった。・・・赤子が腹中で死んでのち固く岩のようになって生まれる病があると聞いた。大明神こと大岩が産ませた子だから石、という解釈とどちらが恐ろしいだろうか。馬琴編「兎園随筆」より。(参照:「大江戸奇怪草子」花房孝典編)
2001/5/19
手というものは、人の器官の中でも妖しいものの宿る感覚に溢れている。首、髪の毛に並んで、化け物として独立して顕れる特性を持っているように思える。
東北地方で、細手の怪として伝えられる話がある。蔦の如き細長い白腕がずーと伸びるというもので、「細手長手」とも呼ばれる妖怪の話だ。何かのすきま・・・大抵は神仏をまつる部屋に接する襖の間や、長押の隙間から、ひょろっと垂れ又伸びてきて、招く。すると、何らかの凶事・・・多くは洪水・・・が起きる。座敷ワラシの類とされることもある。三つ四つの子供の手ほどの大きさで、細く、赤い。轆轤首の腕版の感もある。中国の古い話しに、不意に腕が伸びて、意志に反して動きまわり、しまいに抜けてしまうという話しがあったと思う。亡くなった娘の振り袖を買い取った人が、夜中袖から伸びる白い腕を見て驚いた。「振袖火事」は妖しの振り袖を焼き供養するさいに不意に舞い上がった衣が各所に火をつけて廻ったのが発端とも聞いたが江戸の話、真偽は定かではない。
2001/4/18PM11:30
「蛙石を訪ねて」
日曜に小田原へ行ったのだが何故か疲れが残ってしまい先週にひきつづき風邪気味である。小田原の桜はとっくに終わっていて真新しい天守閣の相模灘を望む景色にのみ感銘を受けた。海の色は湘南なんかに比べて澄んだ水色をしていて、砂浜に花崗岩の丸石が混ざるところに火山帯の近くであることが実感される。海の近くに北条稲荷がある。ここに奇石「蛙石」がある。岩盤のほんの一部が蛙の形で顔を出したものだろうという。ひとかかえくらいのしゃがんだ蛙型の石にはほんものの蛙の瀬戸物がのっていた。鹿島神宮の要石同様いくら掘っても底が見えない。ひところは随分評判のものだったそうだが、小田原に何か異変があるとぐーぐー鳴くといい、後北条氏の危機には一晩中泣き続けたという。地震を予知して鳴くという話しにいたっては、岩盤の一部であるという説に直結するものだ。異変を予知するといえば奈良は飛鳥の亀石を思い出す。巨大なカメ型の石がその向きを変えると飛鳥が水没するという話し。こちらは完全に地上に姿を見せた巨石だから向きを変えられるが、蛙石は地下から顔を出しているだけだからそういうわけにいかないな、などと雑然と思った。
2001/4/9pm3:10
十三塚は日本版マウントともいうべき不思議な古墳群だ。川崎市の各地に点在している。わりあいと小さな(直径5メートルもないとおもう)円形墳が、舌状台地の尾根伝いにずらりと並んでいるさまは壮観。私も数年前一個所だけ見てまわったことがある。大きさからも多分古墳時代の古墳ではなく中世以降の築造のように感じた。形も妙に綺麗なのだ。中央のひときわ目立つ塚を撮ろうとして、カメラのシャッターが切れなくなった。どうやら今でも何か力を発しているのだろう、それだけでもこれが村境を示す単なる標柱のようなものではなく、墓を含む何らかの祭祀遺構であったことがわかる。頭痛がして、それ以上そこにはいられなかったが、雰囲気は穏やかな感じがした。川崎市奥地の丘陵に点在する十三塚の残骸は1984年の段階で7個所(川崎市市民ミュージアム刊「川崎の民俗」より)、けっこう多いのだなと思った。十三という言葉が何を示唆しているのだろうか。よくいわれるのは戦場に散った十三の勇士を埋めた塚(七人の侍の最後のシーンの土饅頭を思い起こす)だとか、行き倒れの十三人を埋めたとか、今でも信仰の対象として残存していることからも何かのいわれがあるには違いなかろう。標識に、近世に流行った雨乞いなどの祭祀遺構という説も否定できまい。十三塚と言ったけれどもじっさいは十三本塚、十三坊、十三人塚、十三菩提、十三峠、十三森、十三騎塚などさまざまな呼び名がある。大きくても5mで人の背丈くらいしかないミニチュア墳丘群で思い出すのは横浜市鶴ヶ峰の畠山重忠が闇討ちに臥したエリア、悲惨な史跡が点在する中で、薬王寺の境内に並ぶ直径2、3メートル程度の六ツ塚を思い出す。境内にならぶ六ツの塚は重忠と一族郎党134名を葬ったものといわれるが、重忠の六人の忠臣の墓とも言われる。いずれもものすごく小さくて、かたつむりのように表面に環を描いた塚があったのには不思議な気がした。呪術に溶け込んだ歴史という言葉が浮かんだ。ついでに七天王塚のことにも触れておこうか。これは千葉大医学部構内に点在するやや大きな塚の群れなのだが、建物や道路をはさんで広範囲に分布するそれらの配置が、柄杓の形、そう北斗七星をかたどっているのだ。北斗信仰に基づくのか、すぐそばに城を構えた千葉氏の菩提を弔うものなのか定かじゃないが、昔は北極星の位置に祠があったというからやはり北斗信仰なのだろう。千葉氏は代々妙見様と呼ばれる北斗を信仰していたともいう。それだけなら不思議でもないが、この塚には別の伝説があって、平将門の七人の影武者を葬ったというのである。将門は千葉の親戚にあたる。不要となった影武者を”処分”しまつったものなのか・・・と少しグロい想像を膨らませる。ここも塚好きならチェックしておくべき場所だろう。粗末にすると祟るとかいうのはどこも共通の伝説だ。
2001/4/8am0:20
さて今日鎌倉行ったのは桜目当てじゃない。ちょっと思い立って、 ”陰明師”安倍晴明ゆかりの物件をみにいったのだ。(以下の話はオンミョウシ(わかりやすくいえば妖怪ハンター)のアベノセイメイを知らないとまったく意味不明になりますのでご注意ください)北鎌倉降りて円覚寺側を大船方向へしばらくあるくと、小高い丘の上に鳥居が見えます。階段をあがるとなんのへんてつもない社殿と、もうひとつさらに小高いところに祠がある。祠に近付くと右手にひらべったい石がある。そして小さな石碑には「安倍晴明大神」の名が。そうこれが、ふれるとたたりがあると村びとから畏れられてきた「晴明石」なのです。一説に晴明がこの地にやってきたとき、禁術をかけたものといわれます。理由はまったく伝わっていません。
ぼくは・・・おそるおそる、右手をのばし・・・
・・・
・・・
左手ものばし、合せて拝んでオワリ。
晴明石はもうひとつ、横須賀線と神宮へむかう幹線がクロスするあたりにもあります。丸い形で奇妙なものでした。どちらもなんの標識もなく、誰にも気をかけられずひっそりと鎮座しておりました。知らずに蹴ったりした人いないのかなあ・・と思いつつ、いくつかお寺をサンサクしたら時間がきたので、待合せの横浜へむかったのでした。
2001/3/28
江戸深川の三十三間堂そばに長いこと空き家になっていた屋敷があって、とある医者が借り受け引っ越してきた。程なく病に倒れ患いつき、この屋敷の湿気が原因だといって薬剤を調合するが一向に効かない。やがて乱心とまではいかないまでも何かに脅え鬱鬱として暮らすようになっていた。
そんな日々のうちにふと思い付くことがあった。物置のほうから冷たい風が流れてくるようで、それに当たると決まって悪感がして正気を失ってしまうということだ。早速弟子に物置に妖しい物がないか調べるように命じた。果たしてひとつも見つからず、古い仏壇があったので中を調べるも何も出ない。
下が扉になってるぞ
弟子のひとりが仏壇の下の袋戸棚に気付いた。開いてみるとはたして、いかにも古い「枕」がひとつみつかった。
医者に報告する。
「これは数百年を経た古物、まさしくこの枕こそ妖怪の正体」
といってただちに庭に焚き火を興し枕を投げ込んだ。
じゅっという音とともに、なんともいえず嫌な匂いがあたりを覆い尽くした。
「・・・こ、これは、先生・・・」
「人の屍の焼ける匂いじゃ」
医者の病はたちどころに回復したそうだ。
(大江戸奇怪草紙より)
2001/2/14
1975年のこと、雲南省建水の宿営地に配属されていた人民解放軍の兵士二人が、夜警を命ぜられゲート前に立っていた。
目前に突然、オレンジ色に光る巨大なUFOがあらわれた。星の見える夜空に忽然と姿を現した光は、あたり一帯を強烈な明かりで照らし出し、兵舎と軍事施設を偵察するかのように、回転しながらあちらこちらと飛び回っていた。
二人はこれは敵の偵察機に違いないと思った。一人が上官に報告に行くことになり、持ち場を離れた。
応援部隊が駆けつけてみると、残るもう一人の姿が見えない。
司令官は即、全員に警戒待機命令を発した。奇襲にそなえ武器と弾薬が用意される。大規模な捜索活動が開始されたが、何ら手がかりがつかめない。数時間が過ぎ、かわりに夜警に立っていた四人の兵士が、かすかなうめき声を聞く。
その主をたどっていくと、兵舎のゲート前に、行方不明の兵士が倒れて、意識朦朧としている。呼びかけて答えはするもののそれ以外の何も答えることができない状態。
兵士に近づいた夜警たちはあっと驚いた。僅か数時間のうちに、髪と髭が、ぼうぼうに伸びていたのである。何週間も剃っていないように見えた。人民解放軍の兵士は丸坊主、髭は厳禁である。何事が起こったのか、兵士たちは顔を見合わせるばかりだった。
当人は結局行方不明だった数時間の間の記憶を一切失っており、ことの真相は闇の中であった。ただひとつ、彼の腕時計は、発見された時には止まっていた。時計と自動小銃は磁気を帯びていたとも言う。この話をのちに聞いた中国のUFO雑誌の編集者は早速当人に取材をしようとしたが、関係者は全て退役し行方知れずとなっていた。退行催眠でも施せば興味深い「宇宙人誘拐」談でも聞けたろうに、と残念がったということである。
~「中国 衝撃の古代遺跡を追う」ハウスドルフ、クラッサ著畔上司訳文芸春秋1996より
2001/2/13
元禄のころ京にとある屏風屋があり齢十二になる息子が居たが、ある日わけもなく高熱を出し寝込んでしまった。
「坊、大丈夫か」
「うーん、うーん」
両親とも枕もとで首をひねるばかり、子供は唸っては、うわごとを繰り返す。
「・・・おなかが・・・おなかが」そのとき襖を開き使いの者が現われた。母親に小袋と白湯のはいった吸口を盆にのせ渡す。
「コレ、熱さましですよ」父親が背を起こさせて、薬包の中身を含ませてやる。
「うーん・・・・・・」
繰り返し水を含ませた手ぬぐいで頭を冷やしてやり、懸命に看病の結果、数日で熱は下がった。
だが、起き上がり歩けるようになった息子に奇妙なことが起こる。
腹に何かできもののようなものが現われたのだ。
それはやがて上下二本の横帯を発し、中央には深い傷口のような裂け目が走った。
「紅くて、まるでクチビルじゃあないか」まるで、もうひとつの口ができたかのようである。母親は恐れて見ようともしない。
覗き込む父親に、息子は弱弱しく口を開く。
「お父、これ・・・しゃべるんだ」
「何を馬鹿なことを」
「だって」
赤ら顔を下に向け、腹のできものにむかって、
「・・・おい、デキモノよう。デキモノよう。」
すると
”なんじゃ”
「お、おい、今の」父親が思わず後ずさりする前で、
”うるさいの、寝ておったところじゃのに”
ぱく、ぱくと”口”が動いて、そのクチビルのあいだから、しゃがれた低い男の声が、響きだしたのである。
これが本当の腹話術というものだ。
「腹がものを言うとは如何」
父親は腹立て、息子は恐れる。口は問い掛ければしゃべるどころか、ずうずうしくも自分から語りかけてくるようになった。さらに、
”おーい、飯を呉れ。飯を呉れ”
口は勝手に食べものをねだるまでになってしまう。
母親が恐る恐る差し伸べた茶碗を前に、掻き開いた袂の奥の口は、付いた腹を引きちぎらんがごとく大口をあけ飯に喰らい付くと、がつがつと音をたてて犬食いする。見る見るうちに息子の腹は膨らんでいくが、口のほうはいっこうに喰うしぐさを休めない。
”少ないのう、もっと呉れ、もっと”空の茶碗の縁を噛みあげると、母親の顔に投げつける。涙をぼろぼろ流す息子の”本体”はといえば、
「もう食べれないよ、いっぱいだよ」だが腹のほうは、
”まだ足りぬ!呉れなくば熱を起こすぞ”
「もうありません」憮然とした母親が空の櫃を傾けると、腹の口は罵詈雑言を投げつける。
”何を言うかこのアバズレめが!まだ米はあるじゃろうが!亭主そろってダメ夫婦か!すぐに炊いて来い、さもなくば”
「えーんえーん」
”うるさい、こん餓鬼が!もうよいわ、こいつ焼き殺してやる、覚悟せい”
言うことを聞かぬと高熱を起こすものだから、従うしかない。仕方なく土間へ向かう母親、おろおろするばかりの屏風屋主人、こんな毎日が続くようになり、家人も気味が悪いわ息子がかわいそうだわ、おまけに大量の飯を消費するからお金も底を突きで、「腹」の恐怖を何とか追い出せないものかとみなそろって頭を捻った。
だがどんな医者に見せても首を捻るばかりで解決の糸口も見えない。
「こんな奇病は見たことがござらぬ。わしには無理じゃ」
「出島で噂を聞いたことはあるが治法はきかなんだ」
「直す手立ては知っておる、だが少々値が張るから、あんたらでは無理だろう」
「直せるのですか、お金は何とかします、ですから是非」
「・・・いやいや、そのためには遠い奥州の山間にあるゴニョゴニョ草が必要ゆえ・・・ゴニョゴニョ・・・」
そんな調子で悉くあてが外れていたところ、菱玄隆という名医と評判の男に行き当たった。
「・・・なるほど」
息子の腹をさすり、噛り付かれないようにすぐ手を引くと、こう言った。
「これは応声虫である。明日また来るがよい、薬を調合しておこう」
そうして翌日息子を伴い現われた屏風屋。すぐに屋敷に上がり、上衣を脱ぐと腹を突き出す。
”ナンダこのへっぽこ医者。おまえなぞにやられるわしではないわ”
「気にすることは無い。これさえ飲ませれば」
ぐっと突き出された医者の手には丸薬が握られている。無理やりに腹に押し込もうとすると、
”ウッこれは”
堅く口を閉ざしてしまい、含ませることができない。
「仕方ない、息子さんに飲ませるが良い。直接飲ませなくとも、効き目は現われてくるはず」
そう言って一袋の丸薬を渡してくれた。
それから毎日丸薬を口に含ませた。上のほうの口にである。
すると、数日が経過して、なんだか腹の口の元気が無い。
”め・・・飯を呉れ・・・”
か細い声で、言われて飯を出さなくとも何も言い返してこない。家人大いに喜んだ。
”たのむ・・・さもなくば・・・”
熱も上がらない。
十日ほどたったころ、息子は不意に腹痛を感じ、厠に駆け込んだ。
すると尻の穴から、細長いものが出てきた。それは長さおよそ一尺の虫で、頭には角を持ち、手足があって蜥蜴によく似ていた。
「きゃーっ」
ずるりと出たあと、虫は必死で逃げ去ろうとする。だがじきに気が付いた家人が追いまわし、滅多打ちして殺してしまった。
以後目に見えて回復し、息子はすっかり健康を取り戻したという。
~原典:天野信景「塩尻」神谷養勇軒「新著聞集」、参考:別冊歴史読本「世界妖怪妖獣妖人図鑑」1996三谷筆項「応声虫」
2001/2/11
世人が突如出奔して山篭る。江戸の昔語りにはしばしば見られる奇人談だが、ここに挙げるは明治の話。「古今東西逸話文庫」より、明治時代の読売新聞の記事になったもの。
京都洛東岡崎に和田政吉という者がいた。所帯を持たずに人力車夫をして生計を立てていたが、二月頃不意に悟るところがあったのか、剃髪して僧侶に少々の経文を教わると、生きながら成仏せん、といって一切の火食を絶ってしまった。そうしてある日飄然と家出をし、鞍馬山に篭ること三十余日、そのあいだ生米を一すくいのほか何も口にしなかった。このほど帰宅したのちも、そのまま火食をせずに過ごしていて、しかし体のほうは少しも痩せ衰える容子も見えず、却って艶々しいとの評判。目下町内の地蔵堂に引きこもり、一心不乱に念仏を唱えるほかは余念無く、その経文も誰に教えられたわけでもないのに自然に「発達」した様子。この男は決して狂人などではなく、言語応対明らかにして何の異状も無い、奇人である。
「百鬼夜話」に昭和の仙人の話を書いた。今でも人里はなれ山篭りする奇人はいなくはないだろう。だが断食一月というのは少々常軌を逸している。山獣や沢蟹を取って喰っていたと勘ぐるのは野暮というものであるが。
2001/2/10
以前江戸のポルターガイストについて書いた(「ポルターガイスト」)。今ひとつ挙げるのは、池尻ならぬ池袋の女の話し。岡本綺堂「風俗江戸物語」に収録されているものだ。ここでも池袋の女を女中などに使うと変事が起きるという言い伝えが、事実として語られている。女が何もせねば何も無いが、屋敷の男とよからぬ仲になったとたんに祟りだす。祟るのは池袋の氏神である。「七面様」と呼ぶ。綺堂が父親のころにはまだあったという麻布「内藤紀伊守の下屋敷」でのこと。ある夜、無数の蛙が現われ、蚊帳の上にまで這って出る。麻布は蝦蟇と縁深い土地だが、女たちにはたまったものではない。逃げ惑う彼女らを嘲笑うように今度は家屋敷がぐらぐらと揺れだす。すわ狐狸の類か、上屋敷より武士が駆り出され、屋敷中をひっくり返して原因を探るも、何も出てこない。遂に十人余の武士が不寝番とあいなった。すると夜も更けた頃ぱたりぱたりとどこからともなく石が降ってくる。一人が鉄砲に手を掛けたとたん、切石が眉間に落ちて、臥し倒れる。畳からも陰火が噴き出し、もう手におえないと一同落胆。だが数ヶ月がたち、女中の一人が池袋の出身であったことが発覚する。しかも出入りの者と密通していることがわかって、これが原因だとばかりに追い出すと、事件はばたりと途絶えたという。綺堂は池袋の女を「代表的江戸の妖怪」と呼んでいる。「耳袋」にある池尻の女の話と非常に似ており、かといって話の出所がはっきりしているからどちらかがどちらかを真似たとも思えない。現代ではどうなのだろうか。
石の降る話しで思い出したが江戸屋敷の怪談として以下の話も伝えられている。菊川某という久留里藩の藩医がいた。根津のあたりに住んでおり、性格剛胆で腕も振るった。その力の源泉は酒で、毎晩大盆を傾けては気を高めていたという。ある夜いつものように一献していると、隣家に妖怪が現われたと伝える者があった。なんでも天から石塔が降ってきて、塵を払うと火が舞い上がるなどし大騒ぎになっているのだという。
面白い。是非我が家にも妖怪に現われてもらいたい
と放言するやいなや。
大音とともに石塔が、庭に降り立った。
だが菊川某、動ずることも無く、カラカラと笑っては尚酒をあおりつづけた。すると傍らにあった行灯が、すーっと宙に浮いたかと思うと、まるで現代の電灯のように、天井の中央に吊り下がってしまった。
ぼうっ
不意の音に目を向けると、隅に置かれた箒から火が舞い上がった。
どーん
またもや石塔が落ちてきた。
そうしてしばらくのうち毎晩変事が続くようになった。本人はいっこうに気にする様子も無かったが困ったのは家中の者。
主が武勇を誇ったために、多くの妖怪を屋敷へ呼び込んでしまったのだ
悲しむもの怨むもの、家族は大騒ぎである。さすがに気にした某、怪事は怖くは無いけれども奥さん怖いとばかりに屋敷を浅草田原町に移すことにした。
だが変事は浅草までついてきた。石塔が降り陰火が舞う。菊川屋敷の噂は世間に広まり、家族の悲しみはおさまらない。
菊川某は遂に藩主に願い上げ、本所石原の江戸下屋敷に住まうこととなった。
だが妖怪はここまでも追ってきた。屋根竹箒より妖しの火が燃え上がり、庭には次々と石塔が降り立つ。その地響きたるや凄まじく、下屋敷の女子供は余りの恐ろしさに戸外へ一歩も出れない始末。同藩江戸家老は留守居役はおろか目付の皆に命じて下屋敷の警備にあたらせ、武勇優れた数十名を菊川居宅に詰めさせて内外を厳重に警備させた。だが相手は妖怪であるから、そんなことでおさまるはずもない。
当時弓術の達人といわれた者がいた。菊川そこへ行ってこれこれこうこうと事情を話すと、同人大いに喜び、
彼の秘法により妖怪を仕留めん
と言い放つや居を正して屋敷へ参った。だが玄関で挨拶をするかしないかのうちに、腰のものが消えている。秘法を行うまでも無く大小を奪われた達人面目無く、屋敷中を捜したところ刀は縁の下より揃って発見された。
その他いろいろと祈祷や祓いを行うもまったく効果はあがらず、さすがの豪傑もほとほとに疲れきってしまった。
のちに湯島の霊雲寺に頼り祈祷してもらったところ真言の効有りでようようと怪事は収まった。庭の石塔を掻き集めてみると数十にもおよび、菊川某は出所の寺をひとつひとつ調べ上げ、全て返したという。
・・・別冊歴史読本「江戸諸藩怪奇ふしぎ事件帳」平川章夫筆、上総久留里藩”江戸屋敷の妖怪騒動”より。
2001/2/7
長浜のホテルに泊まったときのできごと。
チェックインは夕暮れ近く、渡されたカギを手に最上階へ昇る。廊下のいちばん奥の、角部屋だった。窓からの見晴らしもよく設備もきれいで整っている。快適快適と着替えてとりあえず外へ出て、町並みと夕食をたのしむ。7時近く、部屋へ戻るとやっと一息ついた。テレビをつけるとバラエティをやっている。セミダブルに横たわり、ひとしきりテレビに見入りつつ、腹をさすっていると、
うえっ、うえーっ、うっ
という声が耳に入る。えっ?はじめ犬の愚図り声かと思ったが違う。5階だから下の犬の声が届くわけも無い。よくよく耳をすますと隣の部屋なのだ。
ブツブツブツ・・・うっ、ううっ、・・・うえーっ、うっ
これは中年の女の声だ。嗚咽する声に違いない。はじめ押し殺すように、やがてはっきり何事かをつぶやきながら、途切れ途切れの泣き声が響く。
うおーっ、うえっ、うっ、・・・ブツブツブツ
不気味だ。外壁とは逆の、隣室の壁の向こうから、だった。
やだな隣のヤツ。
漠然と思った。
自殺でもするんじゃねえだろうな。
うすら寒い心地も、やがてはじまったコントに笑う我が声にかき消され、私はそのまま寝入ってしまった。
翌朝チェックアウトしに部屋を出る。
声のことはすっかり忘れてカギを閉めると、何気なく隣の扉に目が行った。
・・・番号が無い。
つくりは確かに客室の扉である。
布団部屋は別にあるし位置的にも半端だ。
よく見ると扉の真中にうっすらと、番号を剥がした痕がある。誰か泊まっていようはずもない。
・・・はじめて、
ゾッとした。
2001/2/6
杉並区堀の内は妙法寺に女が出た。
昭和58年9月初め、午後7時過ぎのこと。近所のOLが、犬の散歩に通りかかったとき。
寺の裏には焼き場があって、もともとあまり気持ちの良い場所ではないが、そこに浴衣姿の女が、佇んでいるのが見えた。妙に陰のある感じが気になった矢先、
オン、オンオン
やにわに犬が吠えだす。女に向けて牙を剥き、唸り、吠え立てる。慌てて鎖を引くが、前足を上げばたばたとさせ、今にも飛び掛らんばかりだ。うす暗い境内にけたたましい声が響き渡る。
す、すいません・・・
犬に引きずられるように近づいてしまい、思わず謝った。
だが、女性は微動だにせず、じっと斜め下を向いて、佇んでいる。
ふと着物の柄に目が行った。
胸に子供の顔、足まわりに黒い葉影と紅い小花の一群れ。僅かに揺れている。震えている、と尚も謝ろうとするが、
よくよく見るうちに、それは「柄」ではない。
・・・”向こう”が透けて見えているのだ。
腰から足にかけての薄い布地に、背後の植え込みが透けており、夜風に震えている。その上、胸のあたりには、うしろの墓場の入り口の、地蔵の顔。
!
余りの恐ろしさにへたりこんだ。手放した鎖は地面に落ち、犬は今度は怖気づいたように身をすくめ、弱弱しく唸るばかりである。
浴衣の女は少しずつ、姿を薄らめていく。
花の色が濃くなり、地蔵の顔が白味を増し、街頭の明かりにすかして、姿は
だんだんと薄くなり、
やがてスーっと、消えた。
あとにはまばらに花をつけた植え込みと、古ぼけた石地蔵が残る。
この目ではっきり見た、幻覚なんかじゃない、と後に語った。この寺、同様の話は他にもきかれたという。
~室生忠著「都市妖怪物語」参照
2001/2/5
秀ノ山雷五郎は今の陸中盛岡の出身である。弘化嘉永の頃、横綱力士としてその社会に肩を並べる者がなかった。羽化生(筆者)が幼少の頃は、既に年寄株となって古希に近い老人であったが、この男、左の肩の中に「一文銭」があった。皮膚の上よりありありと見て取れる。いかにしてここに銭が入るはめになったのかと尋ねると、彼が答えるには、
「それがしが子供だった時、一日戯れに寛永通宝を口に含んださい、誤って飲み込んでしまった。泣き叫んで取り出そうと様様に骨を折ったが、かなわなかった。子供心に死んでしまうのだと思って悲しかったが、一日二日と何の事もなくて過ぎ行くうちに、いつしか肩に巡り来て、これこの通りここに現われたのだ」
と言った。
そのためかどうか知らないが、彼の首は左のほうに曲がっていた。
~「古今東西逸話文庫」より、羽化生記
2001/2/4
水戸副将軍光圀在世のころ、ひそかに梓巫女(イチコ)なるものが流行した。
光圀病床にあって心細くなっていたおり、イチコを呼び言った。
「武蔵坊弁慶を寄せよ」
巫女、早速梓弓を取って神おろしの法を行う。しばし眼を閉じていたが、やがて
両目をかっと見開き、大音に呼び
「黄門頭が高い」
と言いはなつ。
黄門暫くの間巫女の顔を熟視してのち、
「我いにしえを慕ふて弁慶を呼び寄せたりしに、頭が高いとは何事ぞ、
我とても従三位中納言なり、何ぞ己れ風情よりかかる言葉を
聞くべき耳なし。無礼ものめ罷り下がれ!」
言い返した。巫女は少しも恐れることなく、
「縁なき我を寄するのみか、かかるいぶせき病床において無礼なり、今一言云はば
その座は立たさぬぞ、黄門何と」
と大音を挙げる。その有り様にさすがの黄門も気味悪いと思ったのであろう、
「よしよし」
と云えば、巫女も法を解いて神を帰した。彼が全国に梓巫女を許したのは唯一度この時
だけだったと伝える。
~「古今東西逸話文庫」より
2001/2/1
若いころの話ですが、スペインのどこかでヒッチハイクをしていて、そのころスペインだけはヒッチハイクはむりだと言われていて、案の定、半日、手を挙げても一台の車もとまってくれず、暑さと疲れでもうろうとし・・・
ふとブレーキの音がしたので顔をあげると、みすぼらしいなりをした貧相な長髪の日本人が、背中のリュックを揺らしながら懸命に走っていって、一台の車に乗り込むのが目に入りました。
それはどう見てもぼく自身で、それもたんに似ているという程度ではなく、着ている物からリュックまでそっくり同じで、こんな汚い格好をしているやつが二人もいるはずがない。思わず、アッ、と声をあげたときには、そいつは車に乗って行ってしまいました。
人は自分のドッペルゲンガーを見ると死んでしまうというじゃないですか。そのことを思いだして、ぼくはゾッとして、もうヒッチハイクどころではなく、急いで駅のほうに向かいました。おかげでまだ死んではいませんが、いまだにあいつはあれからどこに行ったんだろう、とそう考えることがあります。
~山田正紀氏談、ユリイカ1998年8月臨時増刊、総特集 怪談
(同誌なかなか興味深い思索の目白押し。”怪しげ”から”研究”まで、基本的に「創作」に中心点を据えてはいるが、中身が濃い。ホラー作家大アンケート(上記挿話はアンケートから引用)、内田百閒の怪談世界についての論考、杉浦日向子・中沢新一の対談が面白かった)
2001/1/31
・・・人の住む部屋には座敷魔という魔物がいることがあるという。特に病人や心理的なダメージを受けている人の寝間に入り込むらしい。
Iさんの見た座敷魔というのは、Iさんの妹であるK子さんが、何千人に一人という呼吸器の病気で入院していた時、その病室の中であったという。
これが難病だというのでIさんをはじめ、K子さんともども家族全員で、懸命にお祈りしている時、モゾモゾッとK子さんの布団が動く。
「K子!窓開け!」
Iさんが叫ぶと、妙なものが飛び出した。
頭がとがっていて蛇のような目、全身トカゲ色をした長さ五十センチ、幅二十センチくらいの薄っぺらい脚も手もない生き物である。
あわててK子さんが病室の窓を開けると、それはパッと外へ逃げた。
以来、K子さんの病状は見違えるほどよくなったという。
この薄っぺらい生き物は、実は悪霊のひとつで、この座敷魔にずっと棲みつかれたら、その家はすぐに滅ぶのだそうだ。
~中山市朗著「現代妖怪談義 妖怪現わる」遊タイム出版1994
(「新耳袋」で名をはせた著者のとびきり面白い現代妖怪百科より抜粋。式神か憑き物か、およそマンガのような生き物が「実在する」というのだから面白くないわけがない。この本はオススメ)
2001/1/30
幼い頃、竜の子供に出遭った。
そのころこのあたりも郊外の気配を色濃く残しており、家々の間に畑の名残でもあろう草の更地が多くあった。そのひとつで金蛇を追っていた。当時仲間うちで金蛇を捕らえることが一種のブームになっており、どれくらい大きいものを捕まえられるか、グループ同士で競い合っていた。茶色くしなやかな体から長く立派な尾をなびかせて走り去る金蛇を、追う者と待つ者二手に別れて、尾を切らぬよう主尾良く捕らえる。今では影も見ないが、当時かなりの数棲息していたもので、毎日取ってもまだまだ沢山いた。おりしも他のグループが30センチの大物を捕まえたというので、近所中の原っぱを廻ってより大物を探していたときのことである。
原っぱの脇のブロック塀に、緑色に光る物体が見えた。大人の二の腕ほどもある太い幹が、じっと停まっている。よくよく見るうちに、
「・・・何だ」
「何?・・・あっ、すごい・・・」ぎらぎら輝く黒い目、突起の密集した四角い頭。背に居並ぶ長い刺、エメラルドグリーンをベースに虹色に輝く胴体から、鋭い爪のある手足が4つ、ブロックの表面をしっかり掴んでいる。それは2メートルはあろうかという、巨大なトカゲであった。
「つ、つかまえよう」
慌てたわれわれはブロック塀の両側から挟み撃ちにしようと近付いた。怪物は逃げるでもなくじっとしている。
私は尾のほうから手を伸ばして、勢い掴んだ。
「グエッ」
「キャッ」
頭のほうの子が悲鳴をあげる。その子に真紅の大口をあけて襲い掛かったのと、私が尾をつかむのはほぼ同時だった。思わず手を放した目の前から、ばっと飛び上がった大蜥蜴は、先の子の脇をすりぬけ、大きな音をたてて草叢に消えた。われわれは懸命に行方を捜したが、見失った。雨が降ってきた。すぐに豪雨となり、雷が鳴り出した。
・・・あれは怪物だったんだ、雷を呼ぶ妖怪・・・「竜」だったんだということになった。翌日ほかの誰に話しても信じてもらえなかったが、グループのみんなはとてつもない秘密を見てしまったという感動だけで充分な気持ちだった。その後何度もくだんの原に入ったが、やはり見つからなかった。当時遊んだ原っぱで、今でも草原として残っている所は殆ど無いが、怪物のいた原っぱは原っぱのまま現存している。地竜の威光が建物の立つのを拒んでいるのか。サイズを別とすれば、ペットのイグアナかなにかが逃げ出したものだったのかとも思えるが、だいたい当時そんなものを飼っている家があったかどうか、疑問である・・・
2001/1/29
「ところで」ある日、パディ・オホーンと会っていたとき、私はおもむろに切り出しました。「あなたに少しおたずねしたいのです。アイルランドという国は、不思議なことに満ち溢れていますけど、それらはきちんと分類されていません。それらの現象をすべて知ることができれば、ちゃんとしたものを書くのにとても役だつと思うのですが」
「そうですね。私はそんなにたくさんの事を見てきたわけではありませんが、アイルランドで起きた奇妙な出来事についてはたいてい聞いています。それは昔の出来事ではなくて、今なお起きている事なのです。今この時にも、どこかで奇妙な事が起きているんですよ。でも、あなたの興味のある話を私ができればいいんですけれど」
「あなたはレプラカーンに出遭ったことがあると聞いてますが・・・」
「ええそうです。本当です」
「不思議なことですね。ところで、あなたは、沼地で何か奇妙なものを見たというような話はありませんか」
パディは少し考えてから言いました。
「鬼火(”ランプのジャック”)を見たことがあります。たった一度だけですけれど」
「どんなふうでした?」
「そうですね、野うさぎくらいの大きさで、茶色でした。もう少し大きかったかな。ランプを持って、沼地を飛び越えていきました」
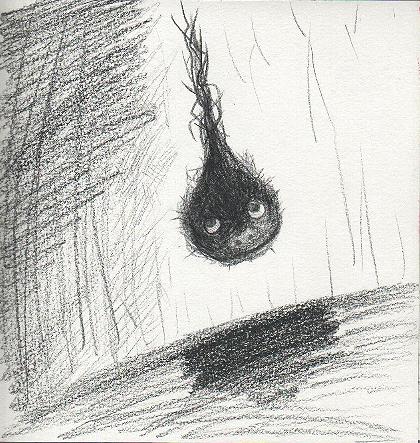
「私がとくに聞きたいのは、おそらく誰もが知りたいことだと思うのですが、鬼火たちは、どんな日常の生態を送っているのですか?」
「日常の生態ですか。鬼火たちは、昼間はほとんど眠っているんですよ」
「しかし夜になると?」私はたずねました。
「そう。夜になると、そう、彼らのおしゃべりから判断すると、彼らが興味を持っているのは、夜おそく外にいる人間たちをどうやって沼地に誘い込むかっていうことですよ。それ以外のことはけっしておしゃべりしません」
「誘い込んで、一体どこに連れていくのですか?」
「彼らの家ですよ、そう、鬼火たちの家にですよ」
「彼らの家はどこにあるのですか?」
「赤と緑の苔が生えているところです。奥深い所にあります。よく彼らの家が”光り苔”でできているといいますが、たしかにそれは鬼火たちにとっての藁葺き屋根のようなものですよ。赤や緑の苔が群生しているところにはどこにでも、その下に鬼火たちが暮らしているんです」
「それで、彼らは人間たちをそこに連れていくんですね」私は確かめるために聞きました。
「もちろんそうです」
「鬼火たちは、どんな話し方をするのですか」
「彼らの声は、大変心地の良い、幽かな聞きなれない感じです。ちょっとうまく言い表わせませんよ。一度聞けば世界中のどんな音とも聞き違えることはありませんよ。しいていえば鴫の羽ばたきの音ですかねえ」
「なぜ彼らは人間たちを沼地の奥深く誘い込むんですか?」私は鬼火たちの活動の一番肝心な点を理解したかったのです。どんな生きものの活動もその動機を知らなければちゃんと理解できませんから。
「そう、彼らは天使や恵み多きものに嫉妬しているんです。彼らは人間たちの魂を奪おうなんて考えてませんよ。ただ、自分たちの傍に置いときたいんです」
「それで、彼らにとって何の得があるんですか?」これでついに、パディ・オホーンから、鬼火たちの生活の本質を聞くことになると私は思いました。
「彼らは、永遠の長い夜の間、人間たちと話をします。”光り苔”の下で。世界に夜の帳が降りて、沼水鶏が鳴いている間、鬼火たちと彼らが誘い込んだ人間たちの魂は、深みの奥で、永久に語り続けるのです」
「しかし、何を話しているんですか?」
「政治についてです」パディ・オホーンは答えました。
~原典:ダンセイニ「フェニックスを食べた男」1949、ヘイニング編著芳賀倫夫訳、深夜画廊「妖精異郷~アイルランドの妖精ABC」国書刊行会1983より
2001/1/28
祖父が人魂を見たのは竹薮であった。拳ほどの小さな炎が無数に集まり漂っていたという。もう百年近くも昔の話しであるけれども、人魂が群れるというのは意外に良くあることらしい。池袋はサンシャインのあたりに、もう20年近く前になろうか、人魂が群れ飛ぶという噂があった。巣鴨プリズンの忌まわしき由来が産み出した恨炎という声があがり、鎮魂の式のうえ現れなくなったと聞いているが本当のところはわからない。羽田沖に旅客機が墜ちたのも昔の話しとなってしまったが、暫くして東京湾に人魂が群れ飛んで悲鳴をあげるという噂が出た。惨事のきたす怪事としてはいささか常套にすぎる有り様だが、黒い水面に遠い漁り火のような燐光を放つ魂の群れる姿を想うとき、悲しくも少し感傷的な気分に陥る。陰火の蒼い灯火は忘れかけた遠い記憶を呼び覚ますようなところがある。「蛍」は人魂と見間違えられることが多いというが、夏の宵の不思議な景を演出する蛍の群れは花火よりも大きな陰影をたくわえ、人の息遣いのように明滅するさまは会話を交わせると思わせるほどでもある。祖父の見たのはまさしく蛍であったのかもしれない。その祖父も今や人魂となってどこかを逍遥している。それとも蛍となってどこかの池のほとりで静かな光を放っているのだろうか。
鎌倉の山間に人造湖があり、女性の幽霊が出るという。山池にありがちな話であるが、この湖はホンモノであると評判だ。はっきりした忌まわしい過去があるでもなく、ただ祟るという噂が人を寄せ付けないのだが、そばに墓地があるらしいし、近くまで入ったとき、不吉な鎌倉でもとくに悪い気配の溜まる感があったから、土地そのものの持つ気が陰に入ってしまう場所なのかもしれない。水気は魂を寄せるというが、人魂が寄り集まることでも有名である。夏に限らないから蛍ではあるまい。ぼうっとした蒼い灯火が幾つも水面に漂う姿は凄まじい、と大分昔に聞いたが、本にも取り上げられずテレビでも見ないし、自分で見てもいないから確証は無い。
木曽御岳かどこかの霊場で、あの世に昇るたくさんの魂が、其の姿を人魂として見せる池があると聞いた。漆黒の闇の中、静かだが何かしら蟠っているような重く生ぬるい空気の底で、メタンが湧くように、ぼこり、と水面が盛り上がり、ぽ、とはぜたあとにぼわんと、人魂のあやふやな姿が顕れて、消灯したばかりの蛍光燈のように、ゆらりと昇る。目を凝らすとその蒼い灯りの中に、人の顔が見えることもある。だがすぐに消える。尾をひいてゆっくり漂うこともあるが、大抵はすぐに見えなくなる。油を塗った器で捕えることができると書いたのは西丸震哉氏であったか、ほんとうに捕らえたことのある人がこの人しかいないだけに信憑性はなんとも言い難い。もしほんとうに人魂であったら、捕獲は人権侵害にならないか?遺族に訴えられないか?自分が死んで、人魂として漂っていたら、捕虫網にかかってしまった。・・・嫌だろうな。ちなみに氏はテントに入ってきたそれを一旦は捕らえたものの逃してしまったそうだ。
2001/1/28
病院は非日常の場所である。通常滅多に出逢うことのない病や怪我が充満し、日常より遥かに高い頻度で「死」が発生する。そんな場では心持ちが非日常であるせいか、妙なものを見てしまう病人も多い。死んだはずの人が顕れる、話し掛けてくる、夜中に首を絞める、向かいの病棟からこちらを見つめている、思いつくまま挙げつらってもこれだけ出てくる。病人の見る「もの」は、強い薬や病そのもののせいであることが多いといわれる。一方看護婦や医者の中にも妙なものを見たり体験したりする人間がいる。往々にして夜中、ナースコールや救急患者の状況に入り交じって発生する「現象」は、過労気味で生活リズムの崩れた時に起こる一種の幻覚とされても仕方ないのかもしれない。「霊感が強い看護婦」というのは怪談のひとつのアイテムといってもいいほどありふれたキャラクターだが、人一倍感受性が強いがゆえ他人の痛みを理解できるタイプの人間が看護婦になりやすいとすれば、感受性の延長上で霊感性を発揮する人間が多いのも理解できるから、彼女の体験を無闇に否定もできまいとも思う。
「あ、この患者さん・・・」
病室に入った瞬間、ふと「見える」ことがある。患者の死が。
けしてそんなことを口にしてはいけない。明かしてはいけない病の重さを知ってしまったならいざしらず、何の問題もなく退院を心待ちにしている患者に、そんなことを言ってはいけない。
退院間際に、何かの手違いであるかのように、ふと亡くなってしまう患者さん。そんな人に出くわすことが何度かあって、そのつど、彼女は何らかの”啓示”を受けていた。
たとえば・・・
「××さん、おかげんはいかがですか。××さん」
「ああ・・・だいぶいいよ。検温だね」
老人は血の気の失せた顔を揺らげて半身を起こした。背後の暗い窓にかかったカーテンが少し揺れている。
「あれ、窓、開けたの」
体温計を手渡しながらカーテンに手を遣る。すると、す、と避けるように揺れ、窓に吸い付いて停まった。更に調べようと手を伸ばすと、患者が背にふれたので目を振り向ける。
「窓なんか開けてないよ」
「そう・・・」
再び回した目に、厚いカーテンが、ずっと微動だにしていないことを主張するかのように、静かに固まっている。嫌な予感がした。
「・・・それじゃ、もうすぐ夕食ですから」
体温計を受け取り、後ろ見に軽く会釈をして出口へと向かう。
「あ、看護婦さん」
「何ですか」
振り向いた彼女は、思わず息を呑んだ。
にこやかにこちらを見る老人の、後ろのあのカーテンの下から、
ずらり、無数の「足」が垂がっている。
一様に細々とした真白い足首、にゅにゅっと突き出し、ぶらぶら、
ざわざわ、
揺れている。
カーテンの揺れた意味がわかった。
「!!」
「どうしたの、看護婦さん。電気、消してってよ」
もう見ないようにしてスイッチを切り、
バタン、扉を閉めた彼女は、今や強烈な予感を抱いていた。
「これって・・・」
でも、そのことを誰にも言えなかった。
食後、不意に老人が・・・身罷るまで。
・・・
まだいろいろあるそうだが、生理的な嫌なビジョンで顕れることが多いという。この「百足」、どちらかというと事象を象徴しているだけの影像で、「幽霊」が其の形をとっていたというわけでもなさそうだが、生々しく奇異なイメージではある。
・・・
2001/1/27
石川某という人が大御番を勤め、上方へ行き来した頃の話しである。
どこの宿場か聞き忘れたが、宿に着いた頃には風雨激しく、まさに大嵐といった空模様になってきた。そのとき宿屋の主が、
「当宿には、このような大荒れの日には、決して人を外に出さないという決め事が有ります。このような日には、人足や馬の賃金さえも受け取りには参りません。なにとぞ、御家来衆にも決して外出しないようにお申し付けください」
と言うので、石川氏の他に三人同僚がいたのだが、それぞれの用人に申し付けて中間たちに外出を禁じたところ、同僚の抱える中間の一人が、
「先ほど休憩をとったところで草履のお金を貸しましたので、是非取りに行きたい」
と懇願した。
「御主人の命であるから、それは叶わぬ」
と固く禁じた。しかししばらくしてまた同じように懇願するので、きつく叱ると、中間は次の間の、葛などが積んである部屋へ行って、ふて寝した。用人は中間の様子が気にかかり、次の間へ行ってみると、果たして中間の姿が見えない。慌てて宿の中を探すがどこにも見つからなかったため、これは宿の外へ出ていったに違いないということになり、主に言うと、
「このような大荒れの日には、この宿では必ず怪事が起こります。ご覧ください。あらゆる戸口には錠を下ろして固く閉ざして有りますので、決して外へ出ることは叶いません」
と答える。さても不思議なことだ、と灯りを点して、さらに隅々を調べると、錠で閉ざした大戸に一寸ほどの節穴があり、節穴とその周りに、おびただしく血が流れているのが見つかった。
「外へ出たいという中間の執念に、何者かが魅入って、あの節穴から引きずり出したに違いない。恐ろしい妖怪がいるものだ」
と一同舌を震って恐れたということだ。
~原典:東隋舎「古今雑談思出草子」、花房孝典編著「大江戸奇怪草子」三五館1997より
2001/1/25
松崎某は福島、平の出身である。実家の近所に松ヶ岡公園というところがあり、子供のときは良く遊んだという。5、6才のころ、日の暮れるにも気付かず夢中で遊んでいると、突然大声がした。
お前たちは、帰らねばならん
驚いてあたりを見回すがどこにも声の主が見当たらない。野太い男の声であった。震え上がった子供たちはみな一目散に逃げ帰った。公園の下に大きな池があり、よく子供が落ちた。おおかた親切な人が声をかけてくれたのだろう、と両親は笑ってとりあわなかった。だが彼は、「ねばならん」という言葉が妙に脳裏に焼き付いて離れなかった。
大きくなった彼は郷里をはなれ上京した。ある日、不思議な夢を見る。
松ヶ岡公園だ
彼はぼんやりと遥か目の下に、なつかしい公園を見下ろしていた。
ちいさな女の子がいた。
・・・由起
5つになる従妹であった。大池のほとりで、柵に乗りあがるようにしてじっと、水面を覗き込んでいる。
危ない
由起の体がぐらりと揺れると、大きな水飛沫があがった。そのとき、どこからともなく大きな「腕」があらわれた。
赤銅色をした逞しい腕が、由起の背中を掴み、ざーっと音をたて、水面高く持ち上げる。
夢はそこまでで終わった。
気になった彼は、郷里の叔母に電話をかけた。
・・・あら珍しいね。
うん、ちょっと気になることがあって。
由起に何か、なかったか?
え・・・別にないんだけど。
そうか・・・
そういえば、昨日泣きながら帰ってきたよ。
なんで?
公園の池に落ちたんだって。びしょびしょでねえ・・・あっ
「おにいちゃん?由起出る、出る」
由起そこにいるの?かわってよ
おにいちゃん、げんき?
明るい声を聞いてはじめて、ほっとした。
おう、元気、元気。由起、池に落ちたんだって?大丈夫か?
だいじょうぶだよ、だって
たすけてくれたんだもん
誰が?
・・・あのね、おっきなおててがね。
叔母の笑う声が聞こえる。
松崎は震えが止まらなかった。
~室生忠編著「都市妖怪物語」三一新書1989を参照
2001/1/24
地元の人が、その人の知っているワシントン州の一家に起きた本当の話だとして教えてくれたことだ。休暇旅行中、その一家がメキシコの国境を越えたあたりでそこの子供のひとりが言った。「ママ、おばあちゃんが起きないよ」。おばあちゃんは死んでいたのだ。その一家はおばあちゃんの遺体を寝袋に入れ、車の屋根にしばりつけ、最初に着いた町で届け出ることにした。警察署に着き、中で手続きをしている間に、遺体ごと彼らの車は盗まれてしまったのだ。遺体も車もいまだ行方不明のままである。また別の人は、この話をイタリアで起きたこととして報告している。
~「消えるヒッチハイカー」ジャン・ハロルド・ブルンヴァン著大月隆寛+菅谷裕子+重信幸彦訳 新宿書房 1988 より
2001/1/23
心霊、オカルトは何故人をひきつけるのだろう。
逃げることができるからなのかもしれない。
日常から隔絶された、夢まぼろしの世界へ。
詰まらないルーティンの日々から、一時でも解き放ってくれるもの。
虚構でも構わない。誤認でも構わないのだ。
テレビでオカルトが取り上げられるたびに、そのマユツバに辟易しながらも、なんとなく見てしまう。・・・楽しんでしまう。この感覚。
インターネットを中心に、近年ふたたび「心霊スポット」ものが流行っている。
「お化け屋敷」と呼ばれる場所に行っては、普段気にも止めないささいな現象に驚き、安いカメラのボケ味を、心霊と言って囃し立てる。カメラの長い露光時間と安いフラッシュの乱暴な灯、さらに湿度の綾が産み出す光る霧状の影を、”心霊”と呼んでいる場合が多い。一昔前は木の葉陰や壁の染みの偶然描き出した”顔”が”心霊写真”の大部分を占めていたものだが・・・。
わかっていて、それでも確信犯的に楽しんでいる人が多いのではないだろうか。嘘とわかっていながらお化け屋敷に入る心理に似ている。ことの真偽はともかく、見ているだけではなく自らを「異界」に投じなければ気がすまないところまで来ていることだけは確かだ。リフレッシュなんて言葉は似合わないが、今や一種のストレス解消剤になっているのだろう。
・・・
本当の死界というものは、取り返しのつかない恐怖と虚無の世界かもしれない。脳が停まれば、何も考えることも、何も思い出すこともできやしない。永遠の虚無が支配するのみだ。それが怖いから、人は死の先に遥かな希望を抱いてきた。生きる苦しみの果てにまったくの虚無が到来するなどという救いようの無い現実を、信じたくない、信じるべきではない。そういった古人の思いが宗教の形をとって今に残る。
だが結局、現実は厳しい。
死後の世界は、多分無い。
とすれば、「能力者」と呼ばれる人々には、いったい「何」が見えているのだろう。
死する人の脳は長く引き伸ばされた時間空間の中に移動するのかもしれない。はたから見ればそのまま朽ちていく屍脳に見えても、その数秒の時間のうちに、脳は果てしの無い未来までも見て、感じて、それは死ぬ当人からすれば、永遠の生を受けたも同然で、死ぬ瞬間の人の「未来の残像」を目にした人が、「幽霊」と感じるものなのではないか。
仮定である。
正月の4日、テレビの恐怖番組を見ていて急に、猛烈に「嫌な気配」をかんじた。その番組は呪われた古墳発掘という趣向で、私も古墳時代で卒論を書いたくらいだから興味深く見ていたのだが、墓場の写真を撮って回ったときの胸の悪さにも似た感じをおぼえた。「それ」は始めテレビの上あたり、そして寝転がる足元へと移動した。煙のような、ごく薄い気配であったが、踵に冷気が触れた瞬間、蛇に睨まれた蛙のように、私は身動きがとれなくなった。テレビから目を離すことも、身をよじることもできない。やっと番組が終わると、解き放たれたが、途端、猛烈な吐き気にみまわれ、次いで腹痛、悪寒。遂には朝まで凍る便所で一睡もできず、それから3、4日の間、寝床から立つこともできなかった。死ぬ苦しみとはこれがえんえんとつづくものに違いない。なんて絶望的なんだ、という思いが脳内をひたすらぐるぐると渦巻く。その前日に頭を打って救急車で運ばれていた。ひょっとすると脳傷か?という恐怖感もあった。脳は検査して無事とわかって、少し安心はしたものの、体調は今もって回復していない。こういう身体的な危機にさいして霊感は薄れるもので、最中は自分しか目に入らず朦朧とするばかりであったが、医者に見せても判然としないまま、ひたすら寝て治すしかなかったこの奇妙な病気・・・あとから考えると何かの悪霊に見込まれたように思えなくも無い。
古墳時代から奈良時代の墓である。もう1300年くらい昔の話しだ。もしこれがあの墓の主の障りであったとしたら、裏返せば、人は1300年間は少なくとも「残像として生きられる」のか。これは希望か?
「異界」という響きには楽園の匂いが感じられる。しかし、「死の苦しみ」がえんえんと続く状態が異界であるとしたら、楽園などという軽やかで美しいものであろうはずがない。
私は夢を見ていた。死は解脱なんかじゃない。もっとリアルで、もっと殺伐としている。
そう回想するとき、
ふと、あの古墳の主が、自分の味わい続ける苦しみを知って欲しい一心で、私の足に取り縋ったビジョンが浮かんだ。
1300年間の苦しみを、少しでも分け伝えたくて・・・。
私は死が恐ろしい。
・・・
2001/1/22
1994年の日記から二項。
・・・
タタミの上、布団がめくれたところに、アルミホイルを丸め、マダラをつけた銀のヒモのようなものがいる。
すと動いて、つと消えた。
目のはしの方、宙に不意にふつふつと、泡がわいて、
ボコボコ消えた。
視界の遠辺に、スーパーボール位の頭が出た。顕れては消えをくりかえし、3m位先のいたるところから顕れてはきえる。小さな缶の中からのぞいたり、窓のカーテンのめくれたところから現れたり。でも、長い間見えていることはなく、明滅する灯台の灯火のように赤い。
精神の歪みのみせる幻か、ひかえめな妖怪のあいさつか。定かではない。
・・・
数年前から流行っているという話し。
女子トイレ。3番目の個室をノックして、「花子さん」と呼ぶと、誰も居ない筈なのに、返事がする。
その個室に入っていると、誰かの足音が近付いてくる。しかしそれきりで何の音もしない。出るさい、ふと隣室が気になって、床の隙間から覗いてみると、「半分だけ」地面から突き出た女の顔が、、、「見たな」
男子トイレ版もあるらしく、話自体は昔からあったものと大差ない。ハナコ(もしくはタロウ)という「名前」があることだけが違う。その名前の存在が、より生生しさを醸し出している。「ピアスの穴」の話しと共にパッと広がったようだ。
ピアスの穴を自分であけようとした少女。焼いた針先を耳たぶにあてがい、一寸痛いが何とか貫通させて、鏡を覗くと、小さな穴の中から、白い糸のようなものが飛び出ている。ほこりでもついたのかな。何気なく手をやり糸を引っ張る。
パッ、とあたりが暗くなる。
それきり少女は失明してしまった。糸は視神経だったのだ。
このまことしやかな噂話は、背筋のこそばゆく、何とも後味の悪い感をあたえる。思いもかけず身近な恐怖。一人旅の危険を伝える「芋虫女」の噂同様、無闇に自分の体を傷つけるな、という諌話に近い。ちなみに芋虫女とは、「東南アジア旅行中に手足を切られ薬漬けにされて地回りのサーカスに売られた女子大生がいた」、というもので、ピアスの白い糸の話と共に広まったが、かなり歴史の古い伝説である。東南アジアではなく大阪の或る土地だったという話も聞いたが(猟奇好きの客のために「作られた」という)、いずれ噂にすぎないだろう。西太后に手足を切られ壷漬けにされた女の話は映画にもなり有名、奇形を見世物にするサーカス団を取り上げた映画「フリークス」にも似たような描写があったように思うから、現代の噂はそのあたりにルーツがあるのは間違い無いだろう。切断という取り返しのつかない惨い仕打ち、見知らぬ土地で全ての救いから隔絶された絶望感・・・身の毛もよだつ。
「都市伝説」というコトバがある。「消えるヒッチハイカー」で取り上げられ有名になった言葉で、単刀直入に言って”ウワサ話”のことである。現代社会における民俗学の研究対象として、松谷みよ子さんらの収集した話が大冊にまとめられているが、学校に通うティーンエイジに広まったこれらはその典型的なものである。学校・・・人が必ずしも自分の意志ではないところで集められた時、そんな場にたちこめる”薄い”不安感が産み出した妄想。私がツクバに入学したてのときも、様々な話が流行った。しかし皆が土地に馴染むにつれ、話題にならなくなっていったものだが、漠然とした不安感が狂暴な噂と化していく過程は、どこかイジメの形成にも通じる気がする。
学校霊で、もっと面白いのがある。
「テケテケ」という。夜半の学校に現れる。ぱっと振り返ると、小さな男がニヤニヤ笑っている。小さいのではない。男には下半身が無いのだ。目が合うと、猛然と追ってくる。足も無いのに、「テケテケ」と足音をたてて・・・
ツクバの宿舎、平砂10号棟(又は11、12という説も。外から全く見えない奥にあり、今はどうだか知らないが、当時は年長の住人だらけで、他の号棟は窮窮としているのに、空き室が多かった11号棟のほうがあやしいといえば怪しかった)に出没した「アディダスの男」は、全国的に有名になってしまい、各地に色々なバリエーションを産んだ。私が入学した時には既に出なくなった後だったが、黄色いアディダスのトレーナーを着た男が、毎晩、部屋の右壁から左壁へと走り抜ける、という話しで、連夜の足音に悩まされた或る学生が、ゴールテープを壁に貼り付けておくと、満足したのか出なくなった、というもの。実はこのオチ付きの話しは後から作られたものらしく、リアルに聞いた話では、廊下を真夜中にダッシュするような足音がして、余りのうるささに文句を言おうと扉を開けると、そこには誰も居ない。そのかわり、並びの部屋の全てから住人が、同じように顔を出して、呆然としていた、という。
変化する噂という点ではこの話しも面白い。夜中男子棟の三階の部屋で勉強していると、窓外、地上三メートルの空中に、いつのまにか女の人が「立って」おり、両腕を水平に差し上げ組んでいて、目が合った途端、組んだ腕を左右にカクカク振りながら、バッと向かってくる。手の動かしかたがピンクレディーの”UFO”の振り付けに似ていることから、「UFO女」と呼ばれていた。これの元話は、勉強に没頭していてふと窓外に目をやると、窓べりに女がもたれかかり、こちらを見てニヤと笑う(三階、だ)・・・というものであったようだが、”UFO女”のほうはしまいにはテレビで女性アイドルが語るくらいにまでひろがっていった。身近に”UFO女”の話しを「作った」、という人がいたせいもあって、噂の広まる勢いに少々驚いたものだ。
他にもある。「星を見る少女」。毎晩”シラノ”よろしく女子棟3階の窓辺で、いつも星を見上げている少女に恋をする男。或る日いてもたってもいられなくなりその部屋へ向かうが扉を叩いても返事が無く、聞けば住人を最近見かけた者がいない。異常だということになり管理人が鍵を開けると・・・窓縁のカーテンレーンに紐を掛け首をくくった少女のミイラ化死体が・・・これは校内の「一の矢」の森だという説もあった。学生の相次ぐ自殺で図らずも有名になってしまった当時の学校を窺わせる噂だ。
まだいくつかあるが、学校のつまらなさを補うかの如きこれらの話の出現は寧ろ歓迎すべきものだったともいえよう。なぜなら抑圧された感情の一つの健全なはけ口になっていたとも考えられるからだ。
・・・
2001/1/21
本郷は桜馬場近くに大店があり、丁稚よりつとめた若い手代がいた。また、田舎から働きに出てきた下働きの娘がいて、二人はいつしか恋仲になった。夜毎近くの桜馬場で逢瀬を繰り返し、
・・・「必ずや夫婦となって添い遂げよう」、
と人知れず深い契りを結ぶまでになったものの、或る日、娘の故郷から主のもとへ、
「婿取りの話がまとまったゆえ、何とぞお暇頂きたい」
との知らせが来た。二人は夜毎桜馬場にて相談し合っては悲嘆に暮れる。江戸の古き世のこと、親の決めた縁談を断ることは不可能、この世で添い遂げることができないのならいっそ、と思い詰めるまでになり、いよいよ婚礼の期日も定まり明日にも暇が出るとわかって、今晩こそ櫻樹に互いに首を縊って果てようと決めてしまう。
「何々時、桜の馬場で・・・」
手代はその日外出の用があって、出かけ間際に娘に囁く。
娘はこくりとうなづいて、唇を噛み締めながら男の両目を見上げた。
・・・用を片づけて暮れ近くになり、手代は桜馬場へと急いだ。着いてみると、娘は既にそこにいた。
「早かったね」
娘は何も言わず、やわらかな笑みだけを差し掛けた。
抱擁し、改めて互いの気持ちを確かめ合う。
心中の心積もりが固まると、手代は手の荷より取り出した長い紐を、ひときわ枝振りの良い櫻樹の枝に投げかけて、二人並んで首を縊る格好となるよう、しっかりと結び付けた。
「良いね」
何も言わず顔を見上げる娘の手をとり、二人して高いところに立つと、二括りの紐を互いの首に掛け合って、もう一度、
「良いね」
「・・・」
背を押し合うように肩を組み、身を寄せ合って、飛び降りた。
首元にがくんという重い衝撃が走る。息も止まり首骨がきしぎしと軋む。だが次の瞬間、男の足先が地に触れた。紐が長すぎたのである。死にきれずもがき苦しむ視界の隅に、そのまま息絶えた娘の、静かに垂がる姿が入った。男はもんどりうって倒れると泡を吹き転げまわって苦しんだ・・・。
「遅くなった」
息せき切って夜道を走る姿があった。娘であった。真っ暗な桜馬場の土手筋を走ると、待ち合わせの木のあたりから、うめくような声が聞こえてくる。不気味に思うも灯りを差し向けて、
「あれッ!」
大声をあげた。草叢に倒れ苦しんでいるのは愛する男、そのそばには何と自分そっくりの娘が、首をくくって死んでいるのだ。
娘の錯乱した声を聞きつけた近住の者が集まってきて、とりあえず男を助け上げ介抱すると、程なく息を吹き返した。心中の訳を聞かれて、男はもう隠すことはあるまいと、正直に事の顛末を淡々と語った。大体の状況はわかったが、わからないのが首を縊った「もうひとりの娘」である。一同は顔を見合わせるばかり、放心状態の手代の腰元にすがる娘は正真正銘本物の生きた娘である。「あれ」をそのままにしておくわけにもいくまい、と桜の枝から下ろし、草中に横たえる。しばらく眺めていると、骸の全身から、ぞろぞろと毛が生えてきて、いつしか狸の姿になっていた。
見た一同大いに驚き、そこへ二人のことを聞きつけた主人が現れる。
「二人とも我が家に良くつくしてくれた。我が家にとっても重宝な人間である。死ぬほどに好きあっているのなら、何も生木を裂くようなことはしたくはない」
と言うと、後日二人の親元へ知らせて、無事添い遂げさせた。
「・・・あの狸は何だったのでしょう」
「もしや俺は毎晩狸と遭っていたのか」
手代がぽつりと呟く横で娘は、
「いいえ、確かに私でした」
と切り返すと、狸塚に向かい腰をかがめて、手を合わせるのであった。
毎夜二人の相談を聞いているうちに同情し、手代を慰めるためにしたことが、誤って自死するはめになってしまったのか、と噂されたが本当のところはわからない。狸は狐と違って明らかな目的も無しに、人間に対し訳のわからぬ悪戯をしかけることがあるが、時折自ずの技にかかっては、愚鈍を示すこともあったようである。
~”耳袋”より。
まぼろしの都について。「蜃気楼」は文字どおり海の蛤の合わせ目から噴き出した気の中に産み出される儚い楼閣、「竜宮城」などもその類、富山湾名物である。今では海面と大気の極端な温度差がレンズのような効果をおよぼし、遠い景色を至近の空中に映し出す科学現象と説明されている。だが人のロマンはそれだけに止まらない伝説を生む。
新約聖書は「ヨハネの黙示録」に描かれる天国の都「新しきエルサレム」、スウィフトが「ガリバー旅行記」に採録した天空の浮島ラピュータは有名。大空を舞い雲と戯れ、気まぐれにその姿をあらわす幻の空中都市は、海面や地面と切っても切り離せない蜃気楼などとは最早別種のものである。
浦島太郎のように、幻の城郭へじっさい足を踏み入れ、異界をかいま見たという噺も、いくつか伝わっている。これらも自然現象を「幻象」の世へとうつしかえた古の人々の強い想像力を感じさせる。現代のロマンにうつしかえればさしずめUFOに乗って宇宙人の住む星を探訪とかいう噺になろうか。
アラスカ上空に、毎年6月21日から7月10日のあいだにあらわれる、イギリスはブリストル市の映像とされるものは、大気現象だけでは説明のつかない遠方の情景であるところが何とも不思議だ。19世紀末には写真にとられ検証までなされるなど話題を呼んだもので、現在も実見されることがあるというが定かではない。
永遠の呪詛に囚われた幻の町の伝説は各所にあるが、イギリスのケルトにつたわる海上沖合にただよう「祝福された死の町」もそのひとつだ。さまよえるオランダ人などといった幽霊船の物語にも通じる。海上にたゆたう「死の市」の姿は恐怖であるとともに、何やら感傷的であるようにも思う。
・・・現実の不可思議がニンゲンの不可思議をくわえて不可思議な伝説となる、いずれ面白い。
奇談ということでたまにはこういったものを。
”天さかるカルホルニヤに見し影の小春に霞む武蔵野の月”
~古今東西逸話文庫(明治27年)第13編より
これが安政のころ、米国公使ハリスの浦賀に来たりし時、幕府に献じた和歌だという。「一時もてはやしけるが、其真偽は知らず、ここに掲げて世の考証を待つ」と原筆者は書き記している。真贋を問うまでもあるまい。唯、麻布は善福寺のハリス顕彰碑をふと思い出した、室町の古に建てられた本堂を前に英文の刻まれる大きな石碑、開国に向かう世の薄明に訪れた若き国の大牛。有名な愛人の話しといい、ペリーの勇壮に比べ伝えられる横顔は生臭さを感じさせるが、こんな茶化た和歌の説もハリスの風体を象徴するかのようにユーモラスだ。
”ポルター・ガイスト”、ドイツのお化けだ。騒霊と訳され、日本では「家鳴り」として親しまれる。夜中に不気味な物音を立てたり、家屋自体が揺れだすといった文字どおり「騒がしい妖怪」で、姿は見えない。それだけであれば、たとえば屋根裏の鼠や乾湿の変化により起こる柱木の軋み、何らかの空気振動に伴う共振といった科学現象に由来するものと一笑に付すことが可能だろうが、例の岐阜の幽霊団地のように、皿や包丁などの台所用品が飛んだり、ひどくなると人が投げ飛ばされたりといったこともある。未成年の特に少女がいる家に発生する確率が高いといい、情緒的に不安定な思春期のもたらす「超能力」が無意識のうちに発揮されたのではないかといわれる。若い処女が何らかの神懸かり的な力を持つという伝承は、魔女然りシャーマン然り洋の東西問わず有るが、それが何らかの理由で抑圧された結果「暴発」したのがポルターガイスト現象だという説は、少し説得力があるように思う。以下に挙げる話しもさしずめその一例と考えられよう。
江戸時代の噺である。幕府の評定所で書役(書記)を勤める大竹栄蔵という人が語った父代の話し。寛保か延享(18世紀半)の頃、ある晩、宅の天井に、大岩の落ちるような音がした。それが怪異の始まりだった。行灯が宙に浮かび、茶碗など食器の類が長押を越え次の間に飛び移ったりなど、次々と起こる。座敷と台所の庭は垣根で境を設けて有ったのだが、或る日雇った米搗きが、台所の庭で米を搗き、一息入れている間に、臼が垣根を飛び越えて、座敷の庭に飛び移ったこともあった。また、天井裏が騒々しいので人を上げて調べてみると、別段何もなかったのだが、降りてきた人の顔に、煤がべったりと付いていたという。やがて座敷で怪火が燃え上がるようなことが頻発するにいたって、火事など起こしたら大事、神主や山伏などを呼んで加持祈祷させるが、いっこうに効果はあらわれない。ほとほと困り果てているうちに知人の老人が、怪異の噺を聞きつけてやってきた。
もしや池尻(現、世田谷区池尻)、もしくは池袋の女を使われてはおりませぬか
と言うから調べてみると、確かに池尻村から来た下働きの女がいて、直ちに暇を出した。果たして怪異はぷっつり途絶えたという。家人不思議に思い後に老人に尋ねたところ、
池尻の産土神(土地神のこと)はたいそう氏子を惜しむ神なり。その土地の女が他所へ出て男と交わるなどすると、必ず妖怪が姿を現すと伝えられる
と。当時大竹氏は子供であったからわからなかったが、恐らく父親がその下女と通じていたのではないか、とも語ったという。
京浜東北線(山手線)新橋駅と有楽町駅の間の線路に、今はどうだか知らないが、「蜘蛛女」があらわれるというウワサがあった。真夜中の車窓からなんとなく外を見ていると、路面に這いつくばってる女が見える。両手両足を虫のように地面に立てて、首だけを上げ、ぎろりと睨む。瞬時、かさかさかさ、と四つんばいで走り、線路脇の電柱によじ登る。下に降りても見ることはできない。京浜東北線の車窓からしか見えず、一瞬だから詳しく観察することもできない。動きはいつも一緒である。そうとうに昔、電車に飛び込んだ女のモノだというが余りにまことしやかな話ではある。
ああいうモノについて考えた。不遇に死んだものが、長いこと浮遊しているうちに、幾つかのモノと合体して、強力な屍力を発することがある。
それはニンゲン同士に限らない。蜘蛛や山羊、犬などの草木動物を併合して、おかしな様相を呈するようになる・・・「蜘蛛女」はそのたぐいだろう。いずれ、まともな神経を維持していることはあるまい。
「やもり女」の話をしよう。地方の古いマンションの、お化け騒ぎについて。小窓の並ぶ建物の北面は、薄汚れたコンクリートで覆われているが、地面から、まっすぐ、最上階のある一室の小窓めがけて、点々と、手のひらのような黒い「掌痕」が浮き上がるという。紐で吊るすような大掛かりなことをしないことには、絶対に打てないであろう垂直の壁のど真ん中にも、左、右、左、右と交叉して続いている。よくみると五本の指のようなものを備えているから手のあとに見えて仕方ない。業者を呼んで消させても、壁の中から浮かび上がるように現れ続ける。ある晩、一人のサラリーマンが奇妙なものを見た。後ろ姿の主婦が、ぼうっと北面を見上げていた。頭の妙に小さい女だと思って近づくと、モノは地面に立っているのではなく、両手のひらを、壁に真っ直ぐ、ぺたり、とつけて、頭ひとつ上のところに、「ぶら下がっている」。垂直腕立て伏せのような格好で、左手から、ぺたり、ぺたりと音をたてて昇っていく最中だったのだ。まっすぐ、まっすぐ上に。その後に、掌の跡が残っていく。べとりと固まりかけた血のような色が月光に鈍くかがやき、余りの景色の生臭さに立ち尽くすうち、主婦のようなソレは20メートルも上の窓に差し掛かった。ずるり。主婦はまるで蛇が配水管に潜り込むように、小窓の中に吸い込まれていった。
その部屋は空き室である。翌日周囲に聞き込んでみるとサラリーマンの予想通り、誤って、その窓から滑り落ちた主婦が、昔いたことが判明した。頭からまっすぐ落ちたから、肩に頭がめり込み、潰れて、半分くらいになっていて、両手は血だらけだった。そのマンションは何故かヤモリが多いという。自然と、「やもり女」という渾名がついた。
別項でも書いたが、ここ2、3年でまったくといっていいほど「霊感」らしきものがなくなってしまった。それどころか、どうやって、どのように見えていたのか、その”感覚”すら思い出せない。物忘れが激しいから、ついこのあいだのことでも忘れることが多くなっていて、霊感なるものについての記憶も、他の雑多と共に流れ去ってしまったようだ。
だからかもしれないが、何か実話怪談風のものを書いても、ウソっぽくなってしまう。5、6年前まで、私は身の回りに「起こった」ことを様々な場所に書き留めていて、そんなものが先ほど、古ノートの間から2つほど出てきた。読むに我ながらなかなか真に迫っている。こういうものを今書けるかというと書けない。その内容はじつは既に「百鬼夜話」にうろ覚えで紹介しているのだが、正直なところリアルタイムの記述に比べて、恐怖感が表面的で、伝わりづらくなっている。おまけに細部が間違っていて、記憶なるものの曖昧さも実感する。それにしてもほんとに、怪談が書けなくなっている。熟考すれば良いものではない。「感覚」が、消えかかっている。
つくづく、時は流れるものだ。降り積もらない。
折角の怪談日記のついでだ、小さな話しを。現在の私が前述の様子ゆえ、薄い話になってしまうのはご勘弁を。
学生のころ、形質人類学で、人骨を組み立てる実習があった。ふるびた枯れ枝のような茶色い骨を、足甲の細かいところまできちんと組み合わせてゆく。全て時間という浄水できれいに洗われて、血管跡のひとつも残らない様だから怖がったり気にしたりする学生もいなかった。私は只、出来上がった人骨の予想外の「小ささ」に胸が縮まる感じがした。自分もこんな姿になってしまうのだろうか。授業はつつがなく終了した。
すっかり忘れてサークルの練習にいそしんだあと、飯を食いに行った。行き付けの蕎麦屋で鳥唐を載せた冷蕎麦を注文する。程なく届いた器を前にごくと喉が鳴り、仲間を待たず箸先に蕎麦をつまんで持ち上げた。ふと、うわっ、と、異様な匂い・・・クレゾールのような強い香り・・・。次いで、肩越しに、何者かの「顔」が覗き込む気がしたのである。
「気がした」ではない。「ビジョンが浮かんだ」のだ。
浅黒い顔。細面で眉毛が濃く、鼻が大きい。黒い髭。額に印?
インド人、という直感が働いた。「食いたがっている」。
だがこいつよりもっと腹が減っている自信があった。練習はそれなりにきつかった。当時霊感もそれなりに力をもっていたと思う。「影」を拭い去るように勢い良く掻き込むと、すっと消えた。
翌日。
友人と前日の実習について話していて、ふと、骨が誰なのか、という話題になった。
あ、あそこの骨はね
聞いた話しだが、と前打ったうえで一人が言うには、こうだった。
輸入らしいよ。戦前とか、昔のことらしいけど、
何でも、インドなんだって・・・
・・・
クレゾールの匂いが・・・ふと鼻をかすめた。